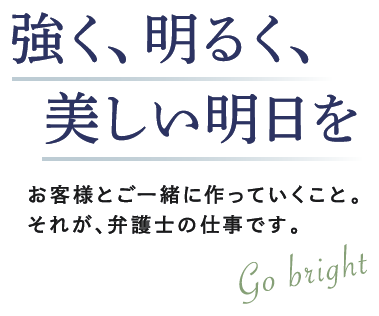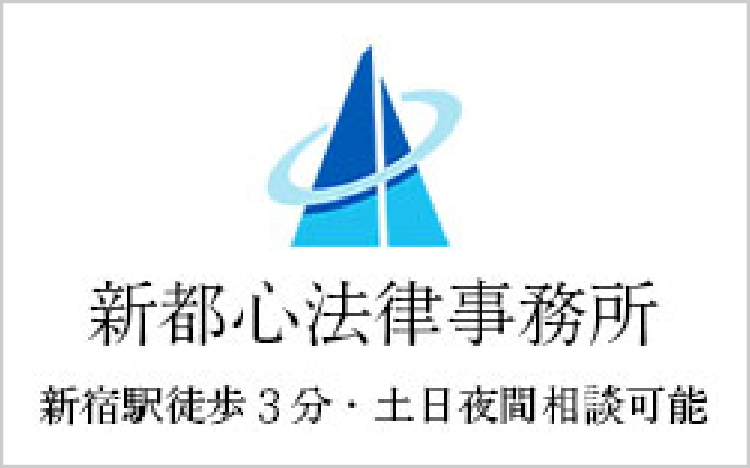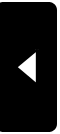2023年02月22日
女に飯をおごらない男と、飯に行くべきか論
男は女に飯をおごるべきか否かってのは、ま、古典的な論点ですが、
最近、タレントさんとか有名なゲーマーさん?などがこれについていろいろおっしゃっているようですが、
野島的には、「おごってくれないんならこの男と飯に行く価値はない」と思ってしまうような男と、飯を食うこと自体が、そもそも、間違いです。
考えてみてください。
どんなに高い飯をおごってもらえるとしてもですよ、どんな、予約困難店の飯であろうと、食べたらどうせうんちになって出るだけです。全然、何も残りません。栄養価的にはもっと、栄養のある食事は山ほどあるはずです。
そのために、そんな、価値のない男につきあって、つまらん話題に合わせるのに気苦労して、何時間も費消して、意味、ありますかね。たとえ、2時間くらい、ああ、おいしいなあ、と思ったとしても、その同じ2時間のあいだ、ああ、つまんねえなあ、この男、めんどくさいなあ、話合わせるの。。。。と思う時間って、楽しいですかね。
わたしは、いやですね。それなら、コンビニ飯を一人で食べてでも、自宅で好きな音楽かけて、好きな本読んだり絵を見たりしながら、食事をしたほうがよほどましです。
どうせ、誰かと一緒にご飯を食べるなら、その時間を楽しく過ごせるほうがいい。一緒に食べて、話して、笑った、楽しかった、って思い出は、これは残ります。うんちにはならんので。
そして、異性と飯を食べるなら、わたしゃ、この男になら、おごってもいい、と思えるような男と以外、飯は食べたくありませんね。
そうじゃないと、食事の時間が、無駄ですよ。私は、そう思います。
まあ、アレです。男の子におごってほしい、っていう女性は、やっぱ、多数います。それはそれで、別に否定すべきことでは全くないと、私は思います。
だけど、「おごってくれないんなら一緒にご飯を食べる価値を認められない」と思ってしまうような相手とは、そもそも、一緒に飯を食う価値がないと思いますよ。それは、相手が男だろうが女だろうが、関係なく、そうなんちゃいますかね。
最近、タレントさんとか有名なゲーマーさん?などがこれについていろいろおっしゃっているようですが、
野島的には、「おごってくれないんならこの男と飯に行く価値はない」と思ってしまうような男と、飯を食うこと自体が、そもそも、間違いです。
考えてみてください。
どんなに高い飯をおごってもらえるとしてもですよ、どんな、予約困難店の飯であろうと、食べたらどうせうんちになって出るだけです。全然、何も残りません。栄養価的にはもっと、栄養のある食事は山ほどあるはずです。
そのために、そんな、価値のない男につきあって、つまらん話題に合わせるのに気苦労して、何時間も費消して、意味、ありますかね。たとえ、2時間くらい、ああ、おいしいなあ、と思ったとしても、その同じ2時間のあいだ、ああ、つまんねえなあ、この男、めんどくさいなあ、話合わせるの。。。。と思う時間って、楽しいですかね。
わたしは、いやですね。それなら、コンビニ飯を一人で食べてでも、自宅で好きな音楽かけて、好きな本読んだり絵を見たりしながら、食事をしたほうがよほどましです。
どうせ、誰かと一緒にご飯を食べるなら、その時間を楽しく過ごせるほうがいい。一緒に食べて、話して、笑った、楽しかった、って思い出は、これは残ります。うんちにはならんので。
そして、異性と飯を食べるなら、わたしゃ、この男になら、おごってもいい、と思えるような男と以外、飯は食べたくありませんね。
そうじゃないと、食事の時間が、無駄ですよ。私は、そう思います。
まあ、アレです。男の子におごってほしい、っていう女性は、やっぱ、多数います。それはそれで、別に否定すべきことでは全くないと、私は思います。
だけど、「おごってくれないんなら一緒にご飯を食べる価値を認められない」と思ってしまうような相手とは、そもそも、一緒に飯を食う価値がないと思いますよ。それは、相手が男だろうが女だろうが、関係なく、そうなんちゃいますかね。
2023年02月21日
離婚相談に、「親」が同行する、ということ。
時々、30代、40代の離婚の相談者さんに、親御さんが同行されることがあります。だいたい、もう、60過ぎの、ご高齢の親御さんです。
ご本人が、ご病気、とくに精神的な疾患をお持ちで、それが深刻である、というなら、まあ、親御さんが心配になるのは判ります。いくつになっても、子どもは子どもですからね。
ですが、そうでもないのに、これくらいの歳の相談者ご本人に、親御さんが同行されると、率直に申し上げて、弁護士としては警戒します。
ひとつは、親御さんがいると、ご本人が本当に率直なご自身の気持ちを言えない、というケースが多々あるからです。
例えば性生活の不一致とか、子といえども、親には言えないことがたくさんあります。
また、特にご本人が男性の場合「ぶっちゃけ、自分はあんまり親権こだわってないんだけど、自分の親が親権にこだわっているんで、、、、」という場合があります。こういう場合も、親御さんが隣にいると、ご本人は弁護士に本音を言えない。これは、弁護士としてはとても困ります。
次に、弁護士が説明義務を負うのは、基本的にはご本人に対してのみ、です。親御さんには、説明責任がありません。たとえ親御さんが弁護士費用を出していても、です。
しかし、同行してくる親御さんは、えてして、契約後、事件が進んで、弁護士がご本人とやり取りをしているさなかに、弁護士に対して「先生、うちの子の離婚、どうなってるんですか」と聞いてくることが多い。
これには、我々は答えられません。まず、弁護士はご本人に対して、守秘義務があります。一度契約すれば、親御さんと言えども他人です。なので、親御さんが電話をかけてきて「どうなってるんですか」と聞かれてもそうそう簡単には、お答えできないのです。
また、仮にお答えした場合、親御さんがご本人に「先生がこんなふうに言っていた」と言い、ご本人が「えっ、そんな話は聞いてないよ」となる、つまりミスコミュニケーションが生じる恐れがあります。そうなると、非常にややこしいですし、ご本人との信頼関係にも影響が生じます。なので、弁護士としては困るのです。弁護士は、事件に関するやり取りの窓口は、ご本人に一本化したいのです。
大切な我が子、という思いは、わかります。しかし、我が子といえども、成人すれば立派な大人です。その人には、その人の人生があり、それは、ご本人が、自己決定されるべき問題です。我が子だけれども、子どもの人生は自分の人生ではない、自分と子どもは違う人格なのだ、ということは、親御さんは頭ではわかっています。しかしそれでもつい、手を出し、口を出し、ひいては子どもの人生決定において、自分の意見を優先させようとする。
これは、親にこういう態度を許しているご本人にも問題があります。
ただ、どうしても気になってしまう、というのも親心でしょう。親御さんは、ご自身が産み育てたご本人を信じ、私の子なのだから、きっと、人生で正しい判断をするに違いない、と信じて、一歩引いて差し上げてください。それがご本人のためです。またそうでないとあとあと、お子さんとの間にトラブルが生じかねません。
あのとき、自分は本当は離婚したくなかったのに、お母さんがうるさく言って離婚させたんじゃないか!こうなったのはお母さんのせいだ!というたぐいの喧嘩は、しばしば発生します。そしてそうなると、親子間の亀裂は、決定的になりかねません。それは、避けた方が良いことです。
ご本人が、ご病気、とくに精神的な疾患をお持ちで、それが深刻である、というなら、まあ、親御さんが心配になるのは判ります。いくつになっても、子どもは子どもですからね。
ですが、そうでもないのに、これくらいの歳の相談者ご本人に、親御さんが同行されると、率直に申し上げて、弁護士としては警戒します。
ひとつは、親御さんがいると、ご本人が本当に率直なご自身の気持ちを言えない、というケースが多々あるからです。
例えば性生活の不一致とか、子といえども、親には言えないことがたくさんあります。
また、特にご本人が男性の場合「ぶっちゃけ、自分はあんまり親権こだわってないんだけど、自分の親が親権にこだわっているんで、、、、」という場合があります。こういう場合も、親御さんが隣にいると、ご本人は弁護士に本音を言えない。これは、弁護士としてはとても困ります。
次に、弁護士が説明義務を負うのは、基本的にはご本人に対してのみ、です。親御さんには、説明責任がありません。たとえ親御さんが弁護士費用を出していても、です。
しかし、同行してくる親御さんは、えてして、契約後、事件が進んで、弁護士がご本人とやり取りをしているさなかに、弁護士に対して「先生、うちの子の離婚、どうなってるんですか」と聞いてくることが多い。
これには、我々は答えられません。まず、弁護士はご本人に対して、守秘義務があります。一度契約すれば、親御さんと言えども他人です。なので、親御さんが電話をかけてきて「どうなってるんですか」と聞かれてもそうそう簡単には、お答えできないのです。
また、仮にお答えした場合、親御さんがご本人に「先生がこんなふうに言っていた」と言い、ご本人が「えっ、そんな話は聞いてないよ」となる、つまりミスコミュニケーションが生じる恐れがあります。そうなると、非常にややこしいですし、ご本人との信頼関係にも影響が生じます。なので、弁護士としては困るのです。弁護士は、事件に関するやり取りの窓口は、ご本人に一本化したいのです。
大切な我が子、という思いは、わかります。しかし、我が子といえども、成人すれば立派な大人です。その人には、その人の人生があり、それは、ご本人が、自己決定されるべき問題です。我が子だけれども、子どもの人生は自分の人生ではない、自分と子どもは違う人格なのだ、ということは、親御さんは頭ではわかっています。しかしそれでもつい、手を出し、口を出し、ひいては子どもの人生決定において、自分の意見を優先させようとする。
これは、親にこういう態度を許しているご本人にも問題があります。
ただ、どうしても気になってしまう、というのも親心でしょう。親御さんは、ご自身が産み育てたご本人を信じ、私の子なのだから、きっと、人生で正しい判断をするに違いない、と信じて、一歩引いて差し上げてください。それがご本人のためです。またそうでないとあとあと、お子さんとの間にトラブルが生じかねません。
あのとき、自分は本当は離婚したくなかったのに、お母さんがうるさく言って離婚させたんじゃないか!こうなったのはお母さんのせいだ!というたぐいの喧嘩は、しばしば発生します。そしてそうなると、親子間の亀裂は、決定的になりかねません。それは、避けた方が良いことです。
2023年02月17日
その弁護士は、仕事が早いか、遅いか。
我々弁護士は書面を書くのが仕事です。時々、しゃべるのが仕事だと思っておられる方がいますが、まあ、しゃべるのもしゃべりますが、書くのが8割です。裁判官もそうですね。
なので、書くのが遅い、または書けない、というのは、我々法律家にとって、致命的です。仕事できないってことですからね。
ところが、ほんとに、「書けない」って方が、たまにいます。そういう方はすごく苦しんでいるのですが、まあ、お客さんとしては、選んではいけない弁護士を選んでしまった。ということになります。
私は自分のしたにいた若手弁護士に、何人かそういうのがいたことがあります。
書面の前で、固まっちゃうんです。なぜ、書けないのだろう、というのを、不思議に思って観察しました。
まず、まあ、弁護士なので頭が悪いわけではないです。が、タイプ1として、頭の中が整理できていない、というひとはいますね。頭の中が整理できていないというか、何を整理していいかわからない。これは、まあ、新人にはいます。経験を積めば改善がみこめるので、このタイプ1は、あまり心配いりません。お客さんには迷惑ですが、しかし、研修医だって、手術してうまくなっていくわけです。ま、誰もが実験台にはなりたくないでしょうが、しかし誰かになってもらわなければならないわけです。
タイプ2。もう新人ではないのに書けないひと、それは、自分に、根本的な、自信がない人です。
どんな弁護士でも、どの方針で書面を書くか、というのは、いろいろ考えて決めるわけです。
こう書けばああ反論されるか?こう書きたいけど、それには証拠が足りないけどどうしよう?こういう主張にしたいけど、これって、法律的に間違ってないよね?などなど、悩みます。
それで、いろいろ比較検討して、決めるわけですけれども、書けない人というのの多くは、比較検討した結果、これがベストだ、これを選ぼう、と決められない人です。
なぜ、決められないかというと、まあ、自分の判断に自信が持てない。というのが、ひとつです。ただ、自分の判断に完全な自信を持てるひとなんてそうそういないわけです。みんな、自信持てないけど、でも、これで書くしかない、と腹をくくって、書くわけです。だって書かなきゃいけませんからね、仕事ですからね。
そこが、覚悟を決めきれない。なぜか。怖いからです。何が怖いのかというともちろんお客さんにベストじゃない選択だったらどうしようっていう怖さもありますが、たいてい、そうじゃない。批判が怖いんです。お前間違ってるだろ、それちがうだろ、という、批判が。
で、なぜ批判が怖いか。その理由の筆頭は、自分に根本的な自信がないからです。自分に、根本的に、自信があれば、少しくらい、批判されたって、ああ、そういう意見もあるな、とか、それくらいで済みます。それで済まないくらい怖い、その理由は、根本的な自信がその人にないからです。
まあ、ボス弁が以上に厳しくて執拗に批判するとかね、部総括裁判官(裁判官の上司みたいなものです)がねちねち批判するとか、そういう場合には、そりゃ、誰もが書けないでしょうが、そういう、誰もが書けないケースではないのに、書けない人、というのは、そもそも人間として、根本的な自信がないことに由来します。
根本的な自信がないから、批判が怖い、批判に異常に傷つく。異常なほどに傷つくから、時に激高して、批判に対してかみつく、許せない。それで感情的な反論をしてしまう。そこでトラブルになる。それでますます書けなくなる。。。。
こうなったら悪循環で、弁護士なら、事案放置で懲戒とかになりかねません。お客さんにとっても大迷惑です。
で、最後に、こういう弁護士を選ばないための、野島なりのコツ、を書いておきます。
それは、その弁護士が、てきぱきしているかどうか。面談の際に、弁護士を、よく見てください。てきぱき、割とはっきりとしゃべる弁護士は、たいてい、さほど遅筆ではないはずです。てきぱきしゃべれる、ということは、自分がしゃべっていることが頭の中で整理されており、かつ、自分がしゃべっていることにある程度、自信がある、ということです。
そういう人を選んでください。そして、選んだら、信用してあげてください。弁護士は、信用されると、張り切っちゃういきものですから。
なので、書くのが遅い、または書けない、というのは、我々法律家にとって、致命的です。仕事できないってことですからね。
ところが、ほんとに、「書けない」って方が、たまにいます。そういう方はすごく苦しんでいるのですが、まあ、お客さんとしては、選んではいけない弁護士を選んでしまった。ということになります。
私は自分のしたにいた若手弁護士に、何人かそういうのがいたことがあります。
書面の前で、固まっちゃうんです。なぜ、書けないのだろう、というのを、不思議に思って観察しました。
まず、まあ、弁護士なので頭が悪いわけではないです。が、タイプ1として、頭の中が整理できていない、というひとはいますね。頭の中が整理できていないというか、何を整理していいかわからない。これは、まあ、新人にはいます。経験を積めば改善がみこめるので、このタイプ1は、あまり心配いりません。お客さんには迷惑ですが、しかし、研修医だって、手術してうまくなっていくわけです。ま、誰もが実験台にはなりたくないでしょうが、しかし誰かになってもらわなければならないわけです。
タイプ2。もう新人ではないのに書けないひと、それは、自分に、根本的な、自信がない人です。
どんな弁護士でも、どの方針で書面を書くか、というのは、いろいろ考えて決めるわけです。
こう書けばああ反論されるか?こう書きたいけど、それには証拠が足りないけどどうしよう?こういう主張にしたいけど、これって、法律的に間違ってないよね?などなど、悩みます。
それで、いろいろ比較検討して、決めるわけですけれども、書けない人というのの多くは、比較検討した結果、これがベストだ、これを選ぼう、と決められない人です。
なぜ、決められないかというと、まあ、自分の判断に自信が持てない。というのが、ひとつです。ただ、自分の判断に完全な自信を持てるひとなんてそうそういないわけです。みんな、自信持てないけど、でも、これで書くしかない、と腹をくくって、書くわけです。だって書かなきゃいけませんからね、仕事ですからね。
そこが、覚悟を決めきれない。なぜか。怖いからです。何が怖いのかというともちろんお客さんにベストじゃない選択だったらどうしようっていう怖さもありますが、たいてい、そうじゃない。批判が怖いんです。お前間違ってるだろ、それちがうだろ、という、批判が。
で、なぜ批判が怖いか。その理由の筆頭は、自分に根本的な自信がないからです。自分に、根本的に、自信があれば、少しくらい、批判されたって、ああ、そういう意見もあるな、とか、それくらいで済みます。それで済まないくらい怖い、その理由は、根本的な自信がその人にないからです。
まあ、ボス弁が以上に厳しくて執拗に批判するとかね、部総括裁判官(裁判官の上司みたいなものです)がねちねち批判するとか、そういう場合には、そりゃ、誰もが書けないでしょうが、そういう、誰もが書けないケースではないのに、書けない人、というのは、そもそも人間として、根本的な自信がないことに由来します。
根本的な自信がないから、批判が怖い、批判に異常に傷つく。異常なほどに傷つくから、時に激高して、批判に対してかみつく、許せない。それで感情的な反論をしてしまう。そこでトラブルになる。それでますます書けなくなる。。。。
こうなったら悪循環で、弁護士なら、事案放置で懲戒とかになりかねません。お客さんにとっても大迷惑です。
で、最後に、こういう弁護士を選ばないための、野島なりのコツ、を書いておきます。
それは、その弁護士が、てきぱきしているかどうか。面談の際に、弁護士を、よく見てください。てきぱき、割とはっきりとしゃべる弁護士は、たいてい、さほど遅筆ではないはずです。てきぱきしゃべれる、ということは、自分がしゃべっていることが頭の中で整理されており、かつ、自分がしゃべっていることにある程度、自信がある、ということです。
そういう人を選んでください。そして、選んだら、信用してあげてください。弁護士は、信用されると、張り切っちゃういきものですから。
2023年02月16日
「突然の別居」が生じたときに。
今年に入ってから、「家に帰ってみたら、妻と子がいなかった=出て行っていた(多くの場合妻と子ですが、お子さんのないご夫婦では、妻だけが消える、ということもあり得ます)」というご相談が続いています。
このご相談には何パターンかあります。
①妻と子と、その荷物が消えており、何の連絡もない場合。
②妻と子と荷物が消えており、妻の置手紙に「弁護士から連絡させます。」と書いてある場合、
③妻と子と荷物が消えており、弁護士からの書面が机の上においてあるとか、あるいは蒸発の2~3日後に届く場合。
①の場合でも、おそらく1週間以内には、何らかの書面が、弁護士なり、妻本人なりから、届くことが多いようです。
いずれのタイプにも、共通することがあります。
第一に、当たり前ですが、これは、別居に向けた行動だということです。つまり、もう夫婦として同居生活を続けることは不可能、という、妻の意思表示です。
第二に、「妻は、かなり前から、相当悩み、考え、いろいろな人に相談し、結論として、突然の別居開始という行動に出ている。」ということです。
第三に言えることは、「このパターンは、夫側に与える精神的ダメージと、怒りが、かなり凄まじい」ということです。
いま、夫とともに家族で暮らしているけれども、どうしても離婚したいんです、と、法律事務所に相談に来た奥さんに対し、弁護士が、それなら別居するしかない、とアドバイスすることは多々あります。子を置いていけない、という奥さんの場合、結果的に子を連れて別居に踏み切ることもあります。これは、「子の連れ去り」の一種ではありますが、現状我が国では、このケースでは、誘拐として、警察が動くことはありません。
もちろん、可能であれば、同居中に何度か、離婚したい、別居したい、という話し合いが夫婦間で、あるいは代理人弁護士を介して、なされ、合意の上で別居したほうが絶対にいい。しかし、同居中にそのような話をすることで、夫が逆上して暴力、暴言罵倒、あるいは経済的な虐待などに及ぶ可能性が高く、それによって、妻や子が受けるダメージが相当程度大である、という場合があります。「同居中に離婚を/別居を切り出す」というのは、配偶者が逆上したときに逃げ場がなく、切り出したほうが、窮地に立たされる可能性が大なのです。主にそのようなときに、妻側が話し合いをせずに、突然消える、という事態が、生じます。
一方、これをされる男性側は、第一にものすごいショックを受け、第二に、強い怒りを感じることが通常です。「家族のことだから家族で話し合ってからにすべきだった」「妻は、家族がバラバラになることに対する、子どもの悲しみを全く理解していない」などと皆さんおっしゃいます。それはそれで、一理あることです。
が、正直に申し上げて、ことここに至ってから、「ああすべきだった、こうすべきだった」などと相手に言ってみたところで、無意味です。相手はもう腹を決めています。そして、相手には相手なりに、そうせざるを得ないいろいろな事情があったのです。
問題は、いまから、あなたが、今後の家族の在り方について、どうしたいのか、について、よく考えて早期に決めること、早期に動くことです。
妻に子供を連れ去られて、別居された、というのは、いわば奇襲攻撃です。奇襲攻撃を受けて、もたもたしていたら、あっというまに本土まで上陸されて焼き払われてしまいます。そうなる前に、体勢を立て直して、挽回の手を打った方がいい。
その、問題の、挽回の手、をどのように考えるかというのは、事案によって全く異なります。
離婚に応じるのか(別居を続けるよりは離婚してしまったほうが、多くの場合、経済的にはメリットが大きい)、子どもに会うことを最優先するのか。まずそこを考えて決めなければなりません。
ただひとつ、ここだけは申し上げておかなくてはならない点があります。妻が、子を連れて別居した、という場合、子を連れ戻す、ということは非常に困難です。お子さんが、15歳以上で、自分の意思がはっきりしていて、やっぱり元の家に戻りたい、と言える場合以外は、連れ戻すことはとても難しい。なぜなら、裁判所は「お子さん、お母さんと一緒なんでしょ。じゃあ、まあ安全でしょう。敢えて裁判所が介入しなくても、お子さんちゃんと生活できるでしょ」と考えるからです。
よくこのようなケースで、「子の引き渡し請求」や「子の引き渡しの仮処分」、をやりたいという方がいます。ですが、まず、仮処分が通ることはめちゃくちゃ稀です。正直、こういう、勝訴見込みの低い処分に弁護士費用を使うのはもったいない、というケースの方が圧倒的に多数です。
それなら、仮処分ではない、いわゆる本案、子の引き渡しの調停、審判の方が、まあ、まだ穏当です。調停で、審判まで行かずに、話し合いで、子を戻せた、ということもないわけではありません。
子どもを連れての突然の別居は、やられた方にとっては「突然」ですが、やった方にとっては、念には念を入れて計画し、長期間暖めてきた作戦なのです。そこをよく理解して、早期に対応されることをお勧めします。家族のかたち、というのは、良くも悪くも、時間が決めてしまう、という側面は、少なからず存在しますので。
このご相談には何パターンかあります。
①妻と子と、その荷物が消えており、何の連絡もない場合。
②妻と子と荷物が消えており、妻の置手紙に「弁護士から連絡させます。」と書いてある場合、
③妻と子と荷物が消えており、弁護士からの書面が机の上においてあるとか、あるいは蒸発の2~3日後に届く場合。
①の場合でも、おそらく1週間以内には、何らかの書面が、弁護士なり、妻本人なりから、届くことが多いようです。
いずれのタイプにも、共通することがあります。
第一に、当たり前ですが、これは、別居に向けた行動だということです。つまり、もう夫婦として同居生活を続けることは不可能、という、妻の意思表示です。
第二に、「妻は、かなり前から、相当悩み、考え、いろいろな人に相談し、結論として、突然の別居開始という行動に出ている。」ということです。
第三に言えることは、「このパターンは、夫側に与える精神的ダメージと、怒りが、かなり凄まじい」ということです。
いま、夫とともに家族で暮らしているけれども、どうしても離婚したいんです、と、法律事務所に相談に来た奥さんに対し、弁護士が、それなら別居するしかない、とアドバイスすることは多々あります。子を置いていけない、という奥さんの場合、結果的に子を連れて別居に踏み切ることもあります。これは、「子の連れ去り」の一種ではありますが、現状我が国では、このケースでは、誘拐として、警察が動くことはありません。
もちろん、可能であれば、同居中に何度か、離婚したい、別居したい、という話し合いが夫婦間で、あるいは代理人弁護士を介して、なされ、合意の上で別居したほうが絶対にいい。しかし、同居中にそのような話をすることで、夫が逆上して暴力、暴言罵倒、あるいは経済的な虐待などに及ぶ可能性が高く、それによって、妻や子が受けるダメージが相当程度大である、という場合があります。「同居中に離婚を/別居を切り出す」というのは、配偶者が逆上したときに逃げ場がなく、切り出したほうが、窮地に立たされる可能性が大なのです。主にそのようなときに、妻側が話し合いをせずに、突然消える、という事態が、生じます。
一方、これをされる男性側は、第一にものすごいショックを受け、第二に、強い怒りを感じることが通常です。「家族のことだから家族で話し合ってからにすべきだった」「妻は、家族がバラバラになることに対する、子どもの悲しみを全く理解していない」などと皆さんおっしゃいます。それはそれで、一理あることです。
が、正直に申し上げて、ことここに至ってから、「ああすべきだった、こうすべきだった」などと相手に言ってみたところで、無意味です。相手はもう腹を決めています。そして、相手には相手なりに、そうせざるを得ないいろいろな事情があったのです。
問題は、いまから、あなたが、今後の家族の在り方について、どうしたいのか、について、よく考えて早期に決めること、早期に動くことです。
妻に子供を連れ去られて、別居された、というのは、いわば奇襲攻撃です。奇襲攻撃を受けて、もたもたしていたら、あっというまに本土まで上陸されて焼き払われてしまいます。そうなる前に、体勢を立て直して、挽回の手を打った方がいい。
その、問題の、挽回の手、をどのように考えるかというのは、事案によって全く異なります。
離婚に応じるのか(別居を続けるよりは離婚してしまったほうが、多くの場合、経済的にはメリットが大きい)、子どもに会うことを最優先するのか。まずそこを考えて決めなければなりません。
ただひとつ、ここだけは申し上げておかなくてはならない点があります。妻が、子を連れて別居した、という場合、子を連れ戻す、ということは非常に困難です。お子さんが、15歳以上で、自分の意思がはっきりしていて、やっぱり元の家に戻りたい、と言える場合以外は、連れ戻すことはとても難しい。なぜなら、裁判所は「お子さん、お母さんと一緒なんでしょ。じゃあ、まあ安全でしょう。敢えて裁判所が介入しなくても、お子さんちゃんと生活できるでしょ」と考えるからです。
よくこのようなケースで、「子の引き渡し請求」や「子の引き渡しの仮処分」、をやりたいという方がいます。ですが、まず、仮処分が通ることはめちゃくちゃ稀です。正直、こういう、勝訴見込みの低い処分に弁護士費用を使うのはもったいない、というケースの方が圧倒的に多数です。
それなら、仮処分ではない、いわゆる本案、子の引き渡しの調停、審判の方が、まあ、まだ穏当です。調停で、審判まで行かずに、話し合いで、子を戻せた、ということもないわけではありません。
子どもを連れての突然の別居は、やられた方にとっては「突然」ですが、やった方にとっては、念には念を入れて計画し、長期間暖めてきた作戦なのです。そこをよく理解して、早期に対応されることをお勧めします。家族のかたち、というのは、良くも悪くも、時間が決めてしまう、という側面は、少なからず存在しますので。
2023年02月06日
スシローぺろぺろ少年の心理の謎
いわゆる、スシローペロペロ高校生の動画で、スシローのみならず、回転ずしの店舗は軒並み客数激減で、大変なことになっているようです。これについて、高校生はスシローに対し、数億くらいの損害賠償責任を負うことになるのではないか、とかいう説も出ていますが、
しかし、厳密にあの行動(ペロペロ→動画撮影→その投稿)でどれくらいの損害が発生したと認定できるかというと、とても難しいだろうと思います。おそらく、せいぜい数百万ではないでしょうか。
また、仮に損害が認められ、損害賠償の判決が出たとしても、そもそもあの高校生と親御さんに支払い能力がなければどうしようもない。一括が無理なら、分割しかなく、あのご家族にはまだ小さいお子さんもいるようですから、せいぜい月に5万程度ではないでしょうか。そうすると年60万、10年かかっても、600万です。それくらい、気の長い話になるでしょう。
こういうとき、よく「払えないでは済まされない!借金してでも払え!」という方がいますが、借金してでも払え、という判決は、わが国では絶対に出ません。勝っても、相手に金がなければ、取れないのです。
判決で勝つことと、現実に回収できることとは全く違います。
しかし、それにしても私が不思議に思うのは、なぜあんなことをするのか、その心理です。
なぜ、そこまで「注目を浴びたい」のか。その手段としてなぜ、「ぺろぺろ」という行為なのか。
想像してみてください。寿司にいちいち唾をつけ、醤油さしを嘗め回す。やるほうにとって、なんら楽しくもなければ、快感もない行為です。
「軽い気持ちで」やった、と親御さんは、言っています。しかし、あの年ごろの子どもたちが「軽い気持ちで」よくやる、「バイクを盗んで集団で走る」「万引きをする」「飲酒、喫煙」といった行為であれば、その行為自体に快感があります。なので、それをやること自体には、まあ、ちゃんとした合理性があります。
ところが、醤油さしをぺろぺろする行為には何の快感もないわけです。それを「動画にとって」さらに「拡散する」、それだけでも楽しくはないでしょう。あの高校生は、それによって「自分が注目を浴びる」ことに、快感を求めているわけです。
そこが、とても不思議に思います。自分にとって快感どころか、めんどくさく、むしろ不快でさえあるであろう行動をわざわざ、手間暇かけて行ってまで、「注目されたい」という、強い欲望。そこまでして「注目されたい」。
その欲望だけが、いびつなまでに大きい。
これはまた、人気者になりたい、称賛されたい、という欲求ともちょっと違うでしょう。醬油さしをぺろぺろしたって、嫌われこそすれ、人気者にはなれないということくらい、わかっているでしょうからね。
たまに、自殺する、自殺する、と言って、わざと親や家族の前を選んで包丁を持ち出してみたりする人がいますが、そういう人たちは、まあ注目を浴びたいわけですよね。称賛されたいわけでもなく、人気者になりたいわけでもなく、ましてや本当に死にたいわけでは全くなく、注目を浴びたい。
その心理は、正直正常ではない。人間誰でも注目を浴びたいとは、心のどこかで思っているものですが、しかし、それにしてもいびつで、病的です。
ぺろぺろ少年は、そのように自分を傷つける方向ではなく、スシローという、赤の他人の店舗に多大な損害を与える方向で、注目を浴びようとしたわけで、それはひっくり返っても許されないことですが、
しかし、そこまでして注目を求める、人気でも称賛でもなく、ただ注目を集める。その、彼の心理はなんなんでしょう。ただの、とんでもないやつ、で済ませられる話なのか。
SNS時代、とかく、「いいね」を集める。注目を集めることに、我々の関心は向いてきています。いいおとなまで、みんな、注目を集めることを、競っている。その風潮に、警鐘を鳴らす事件なのかもしれません。
しかし、厳密にあの行動(ペロペロ→動画撮影→その投稿)でどれくらいの損害が発生したと認定できるかというと、とても難しいだろうと思います。おそらく、せいぜい数百万ではないでしょうか。
また、仮に損害が認められ、損害賠償の判決が出たとしても、そもそもあの高校生と親御さんに支払い能力がなければどうしようもない。一括が無理なら、分割しかなく、あのご家族にはまだ小さいお子さんもいるようですから、せいぜい月に5万程度ではないでしょうか。そうすると年60万、10年かかっても、600万です。それくらい、気の長い話になるでしょう。
こういうとき、よく「払えないでは済まされない!借金してでも払え!」という方がいますが、借金してでも払え、という判決は、わが国では絶対に出ません。勝っても、相手に金がなければ、取れないのです。
判決で勝つことと、現実に回収できることとは全く違います。
しかし、それにしても私が不思議に思うのは、なぜあんなことをするのか、その心理です。
なぜ、そこまで「注目を浴びたい」のか。その手段としてなぜ、「ぺろぺろ」という行為なのか。
想像してみてください。寿司にいちいち唾をつけ、醤油さしを嘗め回す。やるほうにとって、なんら楽しくもなければ、快感もない行為です。
「軽い気持ちで」やった、と親御さんは、言っています。しかし、あの年ごろの子どもたちが「軽い気持ちで」よくやる、「バイクを盗んで集団で走る」「万引きをする」「飲酒、喫煙」といった行為であれば、その行為自体に快感があります。なので、それをやること自体には、まあ、ちゃんとした合理性があります。
ところが、醤油さしをぺろぺろする行為には何の快感もないわけです。それを「動画にとって」さらに「拡散する」、それだけでも楽しくはないでしょう。あの高校生は、それによって「自分が注目を浴びる」ことに、快感を求めているわけです。
そこが、とても不思議に思います。自分にとって快感どころか、めんどくさく、むしろ不快でさえあるであろう行動をわざわざ、手間暇かけて行ってまで、「注目されたい」という、強い欲望。そこまでして「注目されたい」。
その欲望だけが、いびつなまでに大きい。
これはまた、人気者になりたい、称賛されたい、という欲求ともちょっと違うでしょう。醬油さしをぺろぺろしたって、嫌われこそすれ、人気者にはなれないということくらい、わかっているでしょうからね。
たまに、自殺する、自殺する、と言って、わざと親や家族の前を選んで包丁を持ち出してみたりする人がいますが、そういう人たちは、まあ注目を浴びたいわけですよね。称賛されたいわけでもなく、人気者になりたいわけでもなく、ましてや本当に死にたいわけでは全くなく、注目を浴びたい。
その心理は、正直正常ではない。人間誰でも注目を浴びたいとは、心のどこかで思っているものですが、しかし、それにしてもいびつで、病的です。
ぺろぺろ少年は、そのように自分を傷つける方向ではなく、スシローという、赤の他人の店舗に多大な損害を与える方向で、注目を浴びようとしたわけで、それはひっくり返っても許されないことですが、
しかし、そこまでして注目を求める、人気でも称賛でもなく、ただ注目を集める。その、彼の心理はなんなんでしょう。ただの、とんでもないやつ、で済ませられる話なのか。
SNS時代、とかく、「いいね」を集める。注目を集めることに、我々の関心は向いてきています。いいおとなまで、みんな、注目を集めることを、競っている。その風潮に、警鐘を鳴らす事件なのかもしれません。
2023年01月30日
ネット上の名誉棄損
先日、現役の裁判官(仙台高等裁判所)であられる岡口基一裁判官がツイッターで投稿した内容が、名誉棄損に該当するとして、損害賠償(慰謝料)として金44万円の支払いを、岡口裁判官に命じた判決が、東京地方裁判所にて言い渡されました。
44万円という、些か中途半端に見える金額ですが、これは40万円と消費税、ではありません。
賠償金(つまり慰謝料)と、弁護士費用としてその10%、ということです。そしてこの40万円という金額は、この手の事案の慰謝料としては、まあ、そこそこ、高い。と私は考えています。相場の範囲内ではありますが、相場としてはやや、高い方です。
このニュースはかなり大きく報道されました。これを見て、「自分もネット上でいわれのない非難されて/バカにされて/中傷されて/酷いことを書かれて、腹が立って不愉快だ。訴えたら40万円貰えるのか」とか、「ネット上の中傷は世界中に広まるものなのに、たった40万円か」などと、いろんな感想があるでしょう。
ただ、ネット上の誹謗中傷、名誉棄損による損害賠償(慰謝料)請求をお考えの方に、良く理解していただきたいことがあります。それは、
ネット上の名誉棄損等に関する訴訟というものは、
①そんなに簡単に勝てる訴訟ではなく、
②また勝ったところで、認められる金額は少額である可能性が高い、
ということで、逆に言うと「名誉棄損だ!訴えてやる!」と言われて、どうしよう。…と思っている方は、そんなに心配しなくても大丈夫かもしれない。ということです。
今回岡口裁判官の事件は、まずそもそも岡口裁判官ご自身が、異色の裁判官で、平たく言えば「悪目立ち」しておられた、という点は否めません。岡口裁判官は「紛争類型別要件事実」という、司法修習生向けの本をお書きになった方で、我々弁護士のなかでは極めて著名である一方、白いブリーフ一枚のご自身の写真をツイッターに上げられ、法曹界にソコソコ辛口の批評を寄せておられ、一般にも、やや変わった、面白い?裁判官として、広く知られておりました。よくこれを、最高裁が許すもんだなあ、と思っていたのです。
そういう意味で岡口裁判官のツイートは、極めて影響力が大きい。しかも現役裁判官です。このような方がする投稿の影響力と、そうではない、一般人がする投稿とでは訳が違います。岡口裁判官に損害賠償を命じる判決が出たからと言って、一般人が同じことをして同じ判決が出るとは限りません。
また、上記のとおり、訴訟を戦って勝ったとしても得られる金額は少額です。ほとんど、弁護士代にも満たないでしょう。この件の原告さんも、4万円どころではない、数十万単位の金額を、この件のために支出しておられるのではないかなあ、と推察します。
そうなると、弁護士としては、まあ訴えられたら対応しなければなりませんが、こちらから訴えるか、というと、あまり強くお勧めはできない類型の訴訟ではあります。確かに、これはひどいよな、訴訟にするのもやむを得ない、というのもありますが、その見極めには非常に慎重になるべきでしょう。そういう意味では、お客さんが訴えたい!とおっしゃって、弁護士が、はいはい、と訴えていいタイプの訴訟ではない。専門家として、訴えることが、本当にこのお客さんの利益になるのか、よくよく考えるべきタイプの事案です。
なお岡口裁判官は、現在、弾劾裁判という、裁判官を罷免するための特殊な裁判にもかけられています。これは私の物凄く個人的な感想ですが、岡口裁判官に対し、民事訴訟で損害賠償が認められるのは仕方ないとしても(岡口裁判官の社会的地位を考えればなおのことです)、ただ、弾劾して、裁判官を罷免までしなければならないことか、というと、それはまたそれでやり過ぎではないかと思っています。裁判官にも言論の自由がある。それと、裁判官の職責の重さ、社会的地位の高さ、影響力の大きさ、というもののバランスを取ることは、なかなか、難しい作業です。
44万円という、些か中途半端に見える金額ですが、これは40万円と消費税、ではありません。
賠償金(つまり慰謝料)と、弁護士費用としてその10%、ということです。そしてこの40万円という金額は、この手の事案の慰謝料としては、まあ、そこそこ、高い。と私は考えています。相場の範囲内ではありますが、相場としてはやや、高い方です。
このニュースはかなり大きく報道されました。これを見て、「自分もネット上でいわれのない非難されて/バカにされて/中傷されて/酷いことを書かれて、腹が立って不愉快だ。訴えたら40万円貰えるのか」とか、「ネット上の中傷は世界中に広まるものなのに、たった40万円か」などと、いろんな感想があるでしょう。
ただ、ネット上の誹謗中傷、名誉棄損による損害賠償(慰謝料)請求をお考えの方に、良く理解していただきたいことがあります。それは、
ネット上の名誉棄損等に関する訴訟というものは、
①そんなに簡単に勝てる訴訟ではなく、
②また勝ったところで、認められる金額は少額である可能性が高い、
ということで、逆に言うと「名誉棄損だ!訴えてやる!」と言われて、どうしよう。…と思っている方は、そんなに心配しなくても大丈夫かもしれない。ということです。
今回岡口裁判官の事件は、まずそもそも岡口裁判官ご自身が、異色の裁判官で、平たく言えば「悪目立ち」しておられた、という点は否めません。岡口裁判官は「紛争類型別要件事実」という、司法修習生向けの本をお書きになった方で、我々弁護士のなかでは極めて著名である一方、白いブリーフ一枚のご自身の写真をツイッターに上げられ、法曹界にソコソコ辛口の批評を寄せておられ、一般にも、やや変わった、面白い?裁判官として、広く知られておりました。よくこれを、最高裁が許すもんだなあ、と思っていたのです。
そういう意味で岡口裁判官のツイートは、極めて影響力が大きい。しかも現役裁判官です。このような方がする投稿の影響力と、そうではない、一般人がする投稿とでは訳が違います。岡口裁判官に損害賠償を命じる判決が出たからと言って、一般人が同じことをして同じ判決が出るとは限りません。
また、上記のとおり、訴訟を戦って勝ったとしても得られる金額は少額です。ほとんど、弁護士代にも満たないでしょう。この件の原告さんも、4万円どころではない、数十万単位の金額を、この件のために支出しておられるのではないかなあ、と推察します。
そうなると、弁護士としては、まあ訴えられたら対応しなければなりませんが、こちらから訴えるか、というと、あまり強くお勧めはできない類型の訴訟ではあります。確かに、これはひどいよな、訴訟にするのもやむを得ない、というのもありますが、その見極めには非常に慎重になるべきでしょう。そういう意味では、お客さんが訴えたい!とおっしゃって、弁護士が、はいはい、と訴えていいタイプの訴訟ではない。専門家として、訴えることが、本当にこのお客さんの利益になるのか、よくよく考えるべきタイプの事案です。
なお岡口裁判官は、現在、弾劾裁判という、裁判官を罷免するための特殊な裁判にもかけられています。これは私の物凄く個人的な感想ですが、岡口裁判官に対し、民事訴訟で損害賠償が認められるのは仕方ないとしても(岡口裁判官の社会的地位を考えればなおのことです)、ただ、弾劾して、裁判官を罷免までしなければならないことか、というと、それはまたそれでやり過ぎではないかと思っています。裁判官にも言論の自由がある。それと、裁判官の職責の重さ、社会的地位の高さ、影響力の大きさ、というもののバランスを取ることは、なかなか、難しい作業です。
2023年01月24日
セクハラか、それ以外か。
最近、「上司からセクハラをされた」「セクハラされたうえ、写真をばらまかれてしまった」とか、あるいは「部下と恋愛関係にあったのだが、今になってセクハラだと言われている」などのご相談が相次いでいますので、ちょっと、まとめておきたいと思います。
まず、セクシャルハラスメントっていうのはなかなか面倒な問題です。
その理由は、
①ある行為がセクハラか、それ以外の何か(通常の恋愛行動?)該当するかどうかというのは、「(セクハラを)されている方の気持ち」次第だからであり、
②その「されている方の気持ち」というのは本人にしかわからない(しかもその気持ちを本人が相手に伝えないことがあるし、伝えていてもその内容が本当ではないことも多々ある)
③さらにその「されている方の気持ち」というのは、「されているときの記憶」に依存し、その記憶が状況に応じて変化しえる
ためです。
たとえば、会社で、上司が部下に対して、「キスしていい?」と尋ね、部下が頷き、これを受けて上司が部下にがキスをしたとします。その時、部下が、キスされることを「望んで」または「求めて」いたのか、それとも、「仕方ない…」(求めてはいないが、まあ受け入れはする)という思いだったのか、あるいは、「いやだけど、逆らえない」という気持ちだったのかは本人しかわかりません。また人間の記憶というのは「その時の気持ち」をそのまま、長時間維持できるものでもありません。変わっていって当然なんです。このように、外部からはわかりにくく、判ったと思ってもそれが正しいとは限らず、しかもどんどん変わっていく、ひとの「気持ち」というものが、問題の核になるのがセクハラ問題なのです。だから、セクハラ問題はかなり厄介です。双方の認識がどんどんずれていったりします。
なので、(セクハラを)した方は、「僕たちラブラブ、だからキスしただけ、彼女も当然求めていた」と考えていても、
された方は、
①そもそもその時から全然嬉しくない、むしろ嫌だったが、相手が上司だから拒否できなかった、だけだったり、
②その時はまあそのつもりだったが、後日、その上司に注意されてむっとし、「そういえばあの時は本当に嫌だった」と記憶が変わってしまったり、
するわけです。もしかすると、③その時は嬉しかったし、キスを求めてもいたが、後日その上司を嫌いになり、「そういえばあの時も嫌だったんだ」と、記憶が変わってしまうかもしれません。
で、セクハラの訴えが部下から出たとします。キスをした事実自体は間違いない、しかも上司と部下の関係で、会社の中でのことである、部下の方は嫌だったと言っている、となれば、上司の方が、いや、いや、あの時は彼女も喜んでいたんですう、と立証する責任を負います(立証責任、といいます)しかし、「喜んでいた」ことを立証するってのは、かなり困難ですよね、内心のことなので。
じゃあどうしようもないのかというと、例えばキスをした後のラインのやりとりとか、デートしたこととか、手をつないでとった写真とか、そういうもので、「二人の関係は合意に基づく交際関係であり、キスはその一環であって、もちろん合意があった」ことを立証していくことになるわけです。
社内恋愛はよくあることです、それが上司と部下という関係の間でも、恋愛は十分にあり得ます。なので、「上司と部下の関係だから」すべてセクハラと認定されるわけではありません。
しかし、上司と部下との間っていうのは、そもそも、微妙です。なので、まあ、上司と部下で恋愛するとしても、せめて、キスとか抱き合うとかそういう行為は、職場でしないでください。だいたい職場ってそういう場所じゃありません。それ系の行為を行うには、もっと、しかるべき、妥当な場所が、世の中にたくさんあるんです。にもかかわらず、職場でそういう行為をするとなると、それはもう、セクハラって言われちゃっても仕方ないです。それくらいの腹をくくっていただきたいものです。
それでも、どうしても、トラブルになってしまったら、まあ、弁護士に相談された方がいいですよ。当人同士でやると感情が入っちゃいますからね、たいがい、問題が燃え広がります。この類の問題は、冷静に事案を見られる、かつ、そこそこ経験のある、弁護士にゆだねたほうが、皆さんもお楽でしょうし、問題が早く解決するでしょう。
まず、セクシャルハラスメントっていうのはなかなか面倒な問題です。
その理由は、
①ある行為がセクハラか、それ以外の何か(通常の恋愛行動?)該当するかどうかというのは、「(セクハラを)されている方の気持ち」次第だからであり、
②その「されている方の気持ち」というのは本人にしかわからない(しかもその気持ちを本人が相手に伝えないことがあるし、伝えていてもその内容が本当ではないことも多々ある)
③さらにその「されている方の気持ち」というのは、「されているときの記憶」に依存し、その記憶が状況に応じて変化しえる
ためです。
たとえば、会社で、上司が部下に対して、「キスしていい?」と尋ね、部下が頷き、これを受けて上司が部下にがキスをしたとします。その時、部下が、キスされることを「望んで」または「求めて」いたのか、それとも、「仕方ない…」(求めてはいないが、まあ受け入れはする)という思いだったのか、あるいは、「いやだけど、逆らえない」という気持ちだったのかは本人しかわかりません。また人間の記憶というのは「その時の気持ち」をそのまま、長時間維持できるものでもありません。変わっていって当然なんです。このように、外部からはわかりにくく、判ったと思ってもそれが正しいとは限らず、しかもどんどん変わっていく、ひとの「気持ち」というものが、問題の核になるのがセクハラ問題なのです。だから、セクハラ問題はかなり厄介です。双方の認識がどんどんずれていったりします。
なので、(セクハラを)した方は、「僕たちラブラブ、だからキスしただけ、彼女も当然求めていた」と考えていても、
された方は、
①そもそもその時から全然嬉しくない、むしろ嫌だったが、相手が上司だから拒否できなかった、だけだったり、
②その時はまあそのつもりだったが、後日、その上司に注意されてむっとし、「そういえばあの時は本当に嫌だった」と記憶が変わってしまったり、
するわけです。もしかすると、③その時は嬉しかったし、キスを求めてもいたが、後日その上司を嫌いになり、「そういえばあの時も嫌だったんだ」と、記憶が変わってしまうかもしれません。
で、セクハラの訴えが部下から出たとします。キスをした事実自体は間違いない、しかも上司と部下の関係で、会社の中でのことである、部下の方は嫌だったと言っている、となれば、上司の方が、いや、いや、あの時は彼女も喜んでいたんですう、と立証する責任を負います(立証責任、といいます)しかし、「喜んでいた」ことを立証するってのは、かなり困難ですよね、内心のことなので。
じゃあどうしようもないのかというと、例えばキスをした後のラインのやりとりとか、デートしたこととか、手をつないでとった写真とか、そういうもので、「二人の関係は合意に基づく交際関係であり、キスはその一環であって、もちろん合意があった」ことを立証していくことになるわけです。
社内恋愛はよくあることです、それが上司と部下という関係の間でも、恋愛は十分にあり得ます。なので、「上司と部下の関係だから」すべてセクハラと認定されるわけではありません。
しかし、上司と部下との間っていうのは、そもそも、微妙です。なので、まあ、上司と部下で恋愛するとしても、せめて、キスとか抱き合うとかそういう行為は、職場でしないでください。だいたい職場ってそういう場所じゃありません。それ系の行為を行うには、もっと、しかるべき、妥当な場所が、世の中にたくさんあるんです。にもかかわらず、職場でそういう行為をするとなると、それはもう、セクハラって言われちゃっても仕方ないです。それくらいの腹をくくっていただきたいものです。
それでも、どうしても、トラブルになってしまったら、まあ、弁護士に相談された方がいいですよ。当人同士でやると感情が入っちゃいますからね、たいがい、問題が燃え広がります。この類の問題は、冷静に事案を見られる、かつ、そこそこ経験のある、弁護士にゆだねたほうが、皆さんもお楽でしょうし、問題が早く解決するでしょう。
2023年01月17日
細かいことにくよくよするな。
わたしゃ、基本、細かいことを気にしません。
それだけではなく、衣食住全般というか、およそ人生に拘りというものがないのですが、
断っておくがわたしゃ、昔からそうだったのではありません。
ド田舎から大都会東京に、中学2年で引っ越してきて、転校先の同級生には、言葉が違う、服装が違う、持ち物が違うと、もう延々とからかわれ続け、強烈にそれを気にしていました。まあ、まだ13歳とか、思春期の頃でしたしね。
細かーいところまで、東京の同級生のみんなと同じようになりたかったし、みんなに「それ違うよね」と言われるたびにものすごく気にして、気に病んでました。
みんなと同じになりたかった、靴下から髪型まで、どんな些細なところまでも。それを凄く、凄く気にしていたし、みんなに言われた一言一言を、凄く気にしてくよくよしていたのです。
ところが弁護士になってみると、だいたいお客さんというのは、皆細かいことにくよくよして、不幸になっているわけで、
弁護士というのはそういうひとに、そんなことでくよくよしないで、と励ます職業だったのですよ。励ます方がくよくよしていたら、そもそもお話が始まらんのです。
ある時私は突然、それに気が付きました。そしてそれ以来、気にしないと、決意したんですね。決めてしまえば、それは、簡単なことでした。
いまや、自分の外貌外見を一切気にしなくなったどころか、相手代理人から嫌味を言われようが、電車の中でちょっとくらい尻を触られようが、くるしゅうない。良きに計らえ。という感じです。気になりません。減るもんじゃないしね。
なので、だからこそ声を大にして言いたいのですが、みなさん、ああいわれた、こう言われたと、細かいことにくよくよしなさるな。
そんなことしても何の役にも立たないし、それより、今すべきことに集中しましょう。これからの、ことに。
そうしていれば、怖いものは、何もないものです。
それだけではなく、衣食住全般というか、およそ人生に拘りというものがないのですが、
断っておくがわたしゃ、昔からそうだったのではありません。
ド田舎から大都会東京に、中学2年で引っ越してきて、転校先の同級生には、言葉が違う、服装が違う、持ち物が違うと、もう延々とからかわれ続け、強烈にそれを気にしていました。まあ、まだ13歳とか、思春期の頃でしたしね。
細かーいところまで、東京の同級生のみんなと同じようになりたかったし、みんなに「それ違うよね」と言われるたびにものすごく気にして、気に病んでました。
みんなと同じになりたかった、靴下から髪型まで、どんな些細なところまでも。それを凄く、凄く気にしていたし、みんなに言われた一言一言を、凄く気にしてくよくよしていたのです。
ところが弁護士になってみると、だいたいお客さんというのは、皆細かいことにくよくよして、不幸になっているわけで、
弁護士というのはそういうひとに、そんなことでくよくよしないで、と励ます職業だったのですよ。励ます方がくよくよしていたら、そもそもお話が始まらんのです。
ある時私は突然、それに気が付きました。そしてそれ以来、気にしないと、決意したんですね。決めてしまえば、それは、簡単なことでした。
いまや、自分の外貌外見を一切気にしなくなったどころか、相手代理人から嫌味を言われようが、電車の中でちょっとくらい尻を触られようが、くるしゅうない。良きに計らえ。という感じです。気になりません。減るもんじゃないしね。
なので、だからこそ声を大にして言いたいのですが、みなさん、ああいわれた、こう言われたと、細かいことにくよくよしなさるな。
そんなことしても何の役にも立たないし、それより、今すべきことに集中しましょう。これからの、ことに。
そうしていれば、怖いものは、何もないものです。
2023年01月16日
遺骨等を誰が守るのか~祭祀財産の承継者を巡る争い
家族のだれかが亡くなった時に、遺骨を誰が管理し、どこに納骨するのか、というのは、時々争いになります。争いの末、御遺骨や、仏壇を、ウチの事務所でお預かりしたことさえ、あるくらいです。
さら対立が深いとそもそも、「実はきょうだい/おやが亡くなっていたのに、教えてもらえなかった」という事態も時々あります。
遺骨、墓、仏壇を誰が守っていくのか、について対立が深く、ご本人たち同士で話し合いがつかない場合、祭祀承継者指定調停、というものを家裁に起こすことになります。調停で、裁判所が間に入っての話し合いをしても合意が得られなければ、審判と言って、裁判所の判断で決められます。
とはいえ、まあ、審判まで行くことはあまり多くはないのです。多くの事件は、裁判所が間に入って行う調停で、合意できます。
ですが、今般、とうとう、私が担当していたある事件が審判まで進み、このたび無事に、当方のご本人が祭祀承継者として審判において指定されました。
担当する弁護士としては、「裁判所が、審判において、誰が祭祀承継者としてふさわしいか。を決めるとき、何を一番重要な要素として考えているのか?」というのは興味があり、審理を通じて裁判所をよく観察していたのですが、
やはり、「亡くなった方がもし意思表示をするとしたら、誰と指定しただろうか」、つまり亡くなった方の意思を、合理的に推測していくしかないようです。
そのためには、生前からの、亡くなった方と家族とのかかわり方や、どれだけ交流があったかなどを、できるだけ客観的な資料から判断していくわけで、
となると、裁判所に申し立てる側としては、自らと亡くなった方との間に信頼関係があったことを証拠から説明していくように努力していくことになります。
長男だから。長女だから。というだけではだめなのです。
まあ、自分の死後についてご心配な方は、やはり遺言を作成しておかれることをお勧めします。
その方が、争いがなくなるため、遺されたひとたちのためにもなります。
さら対立が深いとそもそも、「実はきょうだい/おやが亡くなっていたのに、教えてもらえなかった」という事態も時々あります。
遺骨、墓、仏壇を誰が守っていくのか、について対立が深く、ご本人たち同士で話し合いがつかない場合、祭祀承継者指定調停、というものを家裁に起こすことになります。調停で、裁判所が間に入っての話し合いをしても合意が得られなければ、審判と言って、裁判所の判断で決められます。
とはいえ、まあ、審判まで行くことはあまり多くはないのです。多くの事件は、裁判所が間に入って行う調停で、合意できます。
ですが、今般、とうとう、私が担当していたある事件が審判まで進み、このたび無事に、当方のご本人が祭祀承継者として審判において指定されました。
担当する弁護士としては、「裁判所が、審判において、誰が祭祀承継者としてふさわしいか。を決めるとき、何を一番重要な要素として考えているのか?」というのは興味があり、審理を通じて裁判所をよく観察していたのですが、
やはり、「亡くなった方がもし意思表示をするとしたら、誰と指定しただろうか」、つまり亡くなった方の意思を、合理的に推測していくしかないようです。
そのためには、生前からの、亡くなった方と家族とのかかわり方や、どれだけ交流があったかなどを、できるだけ客観的な資料から判断していくわけで、
となると、裁判所に申し立てる側としては、自らと亡くなった方との間に信頼関係があったことを証拠から説明していくように努力していくことになります。
長男だから。長女だから。というだけではだめなのです。
まあ、自分の死後についてご心配な方は、やはり遺言を作成しておかれることをお勧めします。
その方が、争いがなくなるため、遺されたひとたちのためにもなります。
2023年01月12日
裁判所オンラインシステムの謎
現在非常に多くの地裁民事部において、オンライン会議システムとしてteams が利用されているのですが、
家庭裁判所では、なぜかteamsではなく、webexを使った運用を始めようとしています。
で、横浜家裁が、他の裁判所に先んじてwebexによる会議を試行しているのですが、
これがなかなか謎な運用なのです。
まず、webexに招待するメールを送るから、メールアドレスを教えろ。という家裁からの連絡が「faxで」来ます。
それから、招待メールを送ったから、webexに参加しろ。という連絡が、「電話で」きます。webexの呼びだし機能ではなく。電話です。
で、ようやくwebexを使った期日が行われるのですが、
それでも、書類のやり取りは「faxで」しろ。というのです。もちろんwebexにも、書類を送受信したり共有する機能はあるのに。です。
うーん。。。。。
これって便利なんでしょうか。。。
そもそも地裁と家裁で何でシステムが違うのかもよくわからないのですが。。。。
謎です。どういう経緯でこんな良くわからないことになってるんでしょ。ただひとつはっきりしているのは、どうやらあのひとたちは、利用者の利便性ってのは、ほとんど考えていないようで、
その結果ご自身もなかなかお忙しいことになっているようです。だってそうでしょう。faxしたり電話したりwebexしたり。ねえ。
もう一度言いますが、これって、ほんとに便利なんでしょうかね。。。。
家庭裁判所では、なぜかteamsではなく、webexを使った運用を始めようとしています。
で、横浜家裁が、他の裁判所に先んじてwebexによる会議を試行しているのですが、
これがなかなか謎な運用なのです。
まず、webexに招待するメールを送るから、メールアドレスを教えろ。という家裁からの連絡が「faxで」来ます。
それから、招待メールを送ったから、webexに参加しろ。という連絡が、「電話で」きます。webexの呼びだし機能ではなく。電話です。
で、ようやくwebexを使った期日が行われるのですが、
それでも、書類のやり取りは「faxで」しろ。というのです。もちろんwebexにも、書類を送受信したり共有する機能はあるのに。です。
うーん。。。。。
これって便利なんでしょうか。。。
そもそも地裁と家裁で何でシステムが違うのかもよくわからないのですが。。。。
謎です。どういう経緯でこんな良くわからないことになってるんでしょ。ただひとつはっきりしているのは、どうやらあのひとたちは、利用者の利便性ってのは、ほとんど考えていないようで、
その結果ご自身もなかなかお忙しいことになっているようです。だってそうでしょう。faxしたり電話したりwebexしたり。ねえ。
もう一度言いますが、これって、ほんとに便利なんでしょうかね。。。。