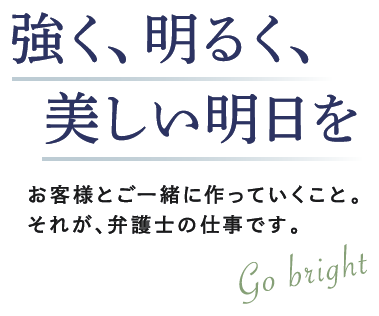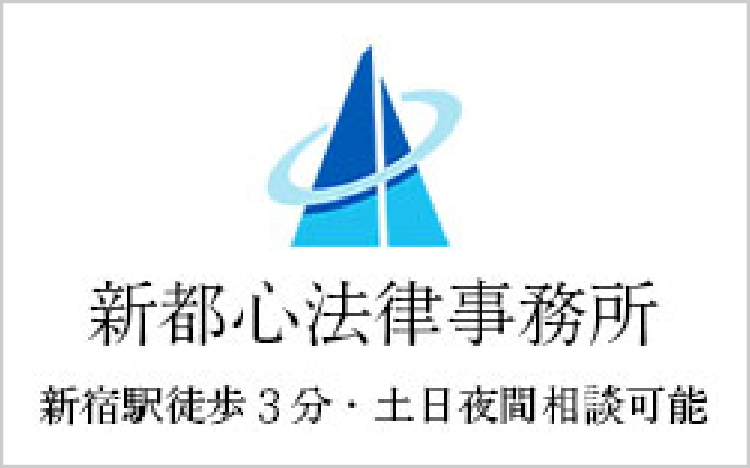2023年01月16日
遺骨等を誰が守るのか~祭祀財産の承継者を巡る争い
家族のだれかが亡くなった時に、遺骨を誰が管理し、どこに納骨するのか、というのは、時々争いになります。争いの末、御遺骨や、仏壇を、ウチの事務所でお預かりしたことさえ、あるくらいです。
さら対立が深いとそもそも、「実はきょうだい/おやが亡くなっていたのに、教えてもらえなかった」という事態も時々あります。
遺骨、墓、仏壇を誰が守っていくのか、について対立が深く、ご本人たち同士で話し合いがつかない場合、祭祀承継者指定調停、というものを家裁に起こすことになります。調停で、裁判所が間に入っての話し合いをしても合意が得られなければ、審判と言って、裁判所の判断で決められます。
とはいえ、まあ、審判まで行くことはあまり多くはないのです。多くの事件は、裁判所が間に入って行う調停で、合意できます。
ですが、今般、とうとう、私が担当していたある事件が審判まで進み、このたび無事に、当方のご本人が祭祀承継者として審判において指定されました。
担当する弁護士としては、「裁判所が、審判において、誰が祭祀承継者としてふさわしいか。を決めるとき、何を一番重要な要素として考えているのか?」というのは興味があり、審理を通じて裁判所をよく観察していたのですが、
やはり、「亡くなった方がもし意思表示をするとしたら、誰と指定しただろうか」、つまり亡くなった方の意思を、合理的に推測していくしかないようです。
そのためには、生前からの、亡くなった方と家族とのかかわり方や、どれだけ交流があったかなどを、できるだけ客観的な資料から判断していくわけで、
となると、裁判所に申し立てる側としては、自らと亡くなった方との間に信頼関係があったことを証拠から説明していくように努力していくことになります。
長男だから。長女だから。というだけではだめなのです。
まあ、自分の死後についてご心配な方は、やはり遺言を作成しておかれることをお勧めします。
その方が、争いがなくなるため、遺されたひとたちのためにもなります。
さら対立が深いとそもそも、「実はきょうだい/おやが亡くなっていたのに、教えてもらえなかった」という事態も時々あります。
遺骨、墓、仏壇を誰が守っていくのか、について対立が深く、ご本人たち同士で話し合いがつかない場合、祭祀承継者指定調停、というものを家裁に起こすことになります。調停で、裁判所が間に入っての話し合いをしても合意が得られなければ、審判と言って、裁判所の判断で決められます。
とはいえ、まあ、審判まで行くことはあまり多くはないのです。多くの事件は、裁判所が間に入って行う調停で、合意できます。
ですが、今般、とうとう、私が担当していたある事件が審判まで進み、このたび無事に、当方のご本人が祭祀承継者として審判において指定されました。
担当する弁護士としては、「裁判所が、審判において、誰が祭祀承継者としてふさわしいか。を決めるとき、何を一番重要な要素として考えているのか?」というのは興味があり、審理を通じて裁判所をよく観察していたのですが、
やはり、「亡くなった方がもし意思表示をするとしたら、誰と指定しただろうか」、つまり亡くなった方の意思を、合理的に推測していくしかないようです。
そのためには、生前からの、亡くなった方と家族とのかかわり方や、どれだけ交流があったかなどを、できるだけ客観的な資料から判断していくわけで、
となると、裁判所に申し立てる側としては、自らと亡くなった方との間に信頼関係があったことを証拠から説明していくように努力していくことになります。
長男だから。長女だから。というだけではだめなのです。
まあ、自分の死後についてご心配な方は、やはり遺言を作成しておかれることをお勧めします。
その方が、争いがなくなるため、遺されたひとたちのためにもなります。