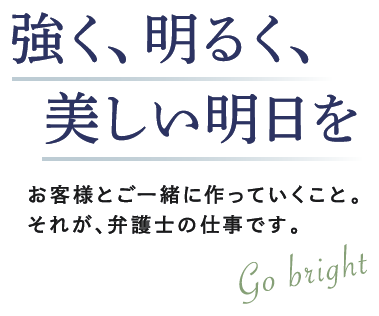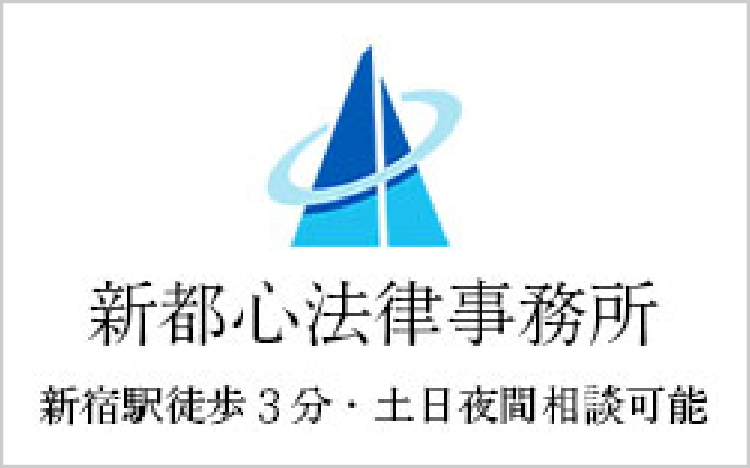2019年04月02日
面会交流と「選択的共同親権」について徒然と思うこと
法務省が、離婚後の、「共同親権」制度の導入検討を始めた、という報道がありました。現在わが国の離婚後の親権は、「単独親権」となっているが、共同親権も選べるようにし、両方の親が子育てに関わりやすくするのが狙い。
というのが、報道です。
うーん…。
まず、親権って何なんだか、多くの方が誤解している、という現実がありますね。
「親権が取れたら、苗字を継がせることができる」というのは間違いですし、
「親権が取れたら、子どもと一緒に生活できる」というのも、必ずしもそうとは限りません。
たぶん皆さんが一番気にしているのって、どちらが子どもと一緒に暮らせるか?ということなのですが、そういう、いわゆる監護権は、親権の一部ではありますが、必ずしも親権そのものではありません。
苗字がどうとかいうのは親権とは関係ないし、相続の権利も親権とは関係ありませんね。
私は国際離婚の案件で、「共同親権」というのが恐るべきトラブルの連続となっている案件を、何度も扱ったことがあるので、共同親権バラ色説には賛同しかねます。
さりとて、離婚後に、子どもが父親とまったく会えないのも問題であり、かつ、面会交流ごとに、いちいち元夫婦が揉め、いがみ合う姿を子供に見せる、というのも問題です。
私は、親権にこだわるお客様には、まずはお客様が実際には何を望んでいるのか(親権がほしい、というのは、具体的には何を望んでいらっしゃるのか)を明確にする作業から入ります。
一方、いまのわが国では父親が親権をとれない、とりにくい。これは非常に非常に非常に大きな問題です。変えなくてはならないのはまずはこの現状の方である。と私は考えています。
おそらく頭の固い裁判官は、父親も母親と同じように子育てをし、子どもと接している、という事態を想定できていないのでしょうね。だから、種たる監護者=母親=親権も母親、という方程式を、何かドグマのように信じているのではないかと疑いたくなる時があります。原始、女性に親権ありき。では、困るときが必ずあるのですから。
男女共同参加とか、女性が輝く社会とか、きれいな言葉を謳うまえに、まずはこういう実態をしっかり見てほしい、とも思います。
この問題は非常に根深くて、簡単に答えが出るものではない。ですが、離婚は子供のあずかり知らぬことです。それによって子どもが不幸になる事態だけは、本当に避けたいものだと、いつも、切に思います。
というのが、報道です。
うーん…。
まず、親権って何なんだか、多くの方が誤解している、という現実がありますね。
「親権が取れたら、苗字を継がせることができる」というのは間違いですし、
「親権が取れたら、子どもと一緒に生活できる」というのも、必ずしもそうとは限りません。
たぶん皆さんが一番気にしているのって、どちらが子どもと一緒に暮らせるか?ということなのですが、そういう、いわゆる監護権は、親権の一部ではありますが、必ずしも親権そのものではありません。
苗字がどうとかいうのは親権とは関係ないし、相続の権利も親権とは関係ありませんね。
私は国際離婚の案件で、「共同親権」というのが恐るべきトラブルの連続となっている案件を、何度も扱ったことがあるので、共同親権バラ色説には賛同しかねます。
さりとて、離婚後に、子どもが父親とまったく会えないのも問題であり、かつ、面会交流ごとに、いちいち元夫婦が揉め、いがみ合う姿を子供に見せる、というのも問題です。
私は、親権にこだわるお客様には、まずはお客様が実際には何を望んでいるのか(親権がほしい、というのは、具体的には何を望んでいらっしゃるのか)を明確にする作業から入ります。
一方、いまのわが国では父親が親権をとれない、とりにくい。これは非常に非常に非常に大きな問題です。変えなくてはならないのはまずはこの現状の方である。と私は考えています。
おそらく頭の固い裁判官は、父親も母親と同じように子育てをし、子どもと接している、という事態を想定できていないのでしょうね。だから、種たる監護者=母親=親権も母親、という方程式を、何かドグマのように信じているのではないかと疑いたくなる時があります。原始、女性に親権ありき。では、困るときが必ずあるのですから。
男女共同参加とか、女性が輝く社会とか、きれいな言葉を謳うまえに、まずはこういう実態をしっかり見てほしい、とも思います。
この問題は非常に根深くて、簡単に答えが出るものではない。ですが、離婚は子供のあずかり知らぬことです。それによって子どもが不幸になる事態だけは、本当に避けたいものだと、いつも、切に思います。