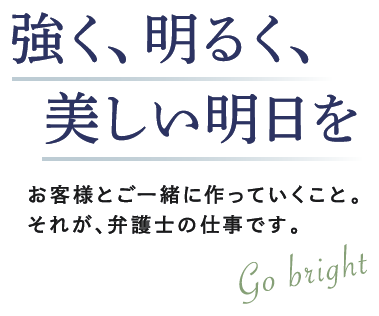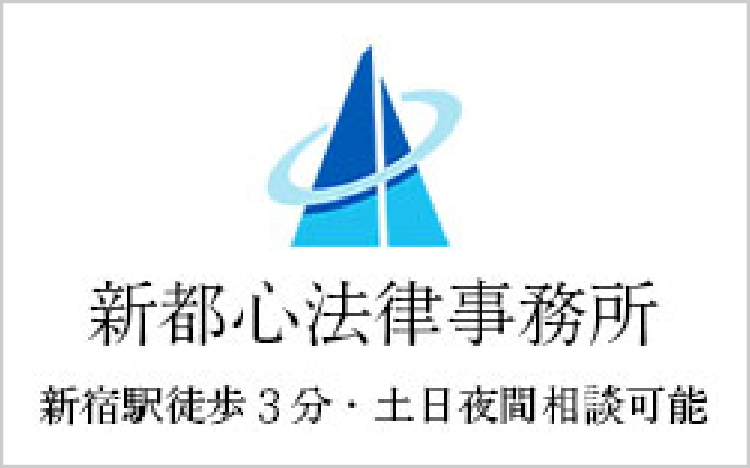2024年02月02日
「方言禁止」なるお笑い番組について
お笑い番組で、地方出身の芸人に「方言禁止」にチャレンジさせる、っつう番組が差別かどうか、という話題で、私は、北海道から東京に来た13歳の時を思いだしました。
当時私は、自分が訛っているとは思っていなかったのですが、東京人からすると、やはり訛っていたようです。
例えば、椅子、の発音が違ったようで、同級生は私に敢えて、「これは何?」と聞き、私が「椅子」と答えると、どっと笑うのです。
また、「7」の発音が違ったようで、私に、「1,2,3,4,5,6」の次は?と聞き、私が「7」というと、どっと笑うのです。そして、いなかっぺ、いなかっぺ、とはやし立て、消しゴムや、鉛筆などを投げつける。ということが、多くありました。
だから私は、教室で方言を出したくなかったのです。でも、自分の発音のどこが、皆と違うのか、わからなかった。皆と同じになりたかった。切実になりたかったのだが、自分のどこが人と違うのかが、判らなかったんです。
そんなとき、私は一人でふらっと、井の頭公園動物園に行って、サル山を見ました。そこでは、子ザルたちが、一匹の子ザルをいじめていた。サルたちは、その一匹を、池に突き落とし、這い上がろうとすると妨害し、這い上がったらまた池に突き落とそうと追い回していました。
それを見て、私は、はっと気が付いたのです。
サルたちにはこの子ざるが、何か、自分たちと違うところがある、思って苛めているのだろうが、人間から見ると、別にこの子サルには、ほかの子ザルと、何ら違いはない。たとえ違いがあるとしても、それは些細なこと、さる山という、狭いコミュニティの中での違いでしかない。
広い世界から見ればそんな違いは何でもない。みんな等しく、サルである。そして、その些細な違いについて、虐められている子サルには、何の非もない。
それと同じように、たとえ、私の発音が多少違っても、私が多少ほかの人より痩せていても、見ているテレビや読んでいる本が違っても、多少考え方が違っていても、そんなのはおそらく、広い世界から見たらほぼどうでもいい違いなのだ。
そして、私が、そのほぼどうでもよい違いを嘲笑されたとしても、それは嘲笑する方が悪いのだ。私には一切非がない。だから堂々としていればいいのだ。私は既に、十分皆と同じなんだ。ひがむことも否定すべき点も、ない。
私は、そう思いました。
以来、私は、方言をからかわれることや、「へん」とか「おかしい」とか言われることが一切気にならなくなりました。
この時から、私は、自分はほかの人と、一切違いはない、全く標準の人間である、と確信しています。自分に個性なんかあってたまるか、個性なんかくそくらえ。今でもそう思っています。我々は、みんな等しく、サルなのです。
なので、本題に戻りますと、この「方言禁止」なる番組には、差別という要素もあろうが、本質的には、多数派が、ほぼどうでもいい些細な違いをあげつらって、少数派を虐めて楽しむ、という図、
どこの社会でもよく見られる図なのだろうと思います。
しかし、決して褒められた図ではありません。こういうお笑いしかできないお笑い芸人というのに、どれだけ存在意義があるのでしょう。
当時私は、自分が訛っているとは思っていなかったのですが、東京人からすると、やはり訛っていたようです。
例えば、椅子、の発音が違ったようで、同級生は私に敢えて、「これは何?」と聞き、私が「椅子」と答えると、どっと笑うのです。
また、「7」の発音が違ったようで、私に、「1,2,3,4,5,6」の次は?と聞き、私が「7」というと、どっと笑うのです。そして、いなかっぺ、いなかっぺ、とはやし立て、消しゴムや、鉛筆などを投げつける。ということが、多くありました。
だから私は、教室で方言を出したくなかったのです。でも、自分の発音のどこが、皆と違うのか、わからなかった。皆と同じになりたかった。切実になりたかったのだが、自分のどこが人と違うのかが、判らなかったんです。
そんなとき、私は一人でふらっと、井の頭公園動物園に行って、サル山を見ました。そこでは、子ザルたちが、一匹の子ザルをいじめていた。サルたちは、その一匹を、池に突き落とし、這い上がろうとすると妨害し、這い上がったらまた池に突き落とそうと追い回していました。
それを見て、私は、はっと気が付いたのです。
サルたちにはこの子ざるが、何か、自分たちと違うところがある、思って苛めているのだろうが、人間から見ると、別にこの子サルには、ほかの子ザルと、何ら違いはない。たとえ違いがあるとしても、それは些細なこと、さる山という、狭いコミュニティの中での違いでしかない。
広い世界から見ればそんな違いは何でもない。みんな等しく、サルである。そして、その些細な違いについて、虐められている子サルには、何の非もない。
それと同じように、たとえ、私の発音が多少違っても、私が多少ほかの人より痩せていても、見ているテレビや読んでいる本が違っても、多少考え方が違っていても、そんなのはおそらく、広い世界から見たらほぼどうでもいい違いなのだ。
そして、私が、そのほぼどうでもよい違いを嘲笑されたとしても、それは嘲笑する方が悪いのだ。私には一切非がない。だから堂々としていればいいのだ。私は既に、十分皆と同じなんだ。ひがむことも否定すべき点も、ない。
私は、そう思いました。
以来、私は、方言をからかわれることや、「へん」とか「おかしい」とか言われることが一切気にならなくなりました。
この時から、私は、自分はほかの人と、一切違いはない、全く標準の人間である、と確信しています。自分に個性なんかあってたまるか、個性なんかくそくらえ。今でもそう思っています。我々は、みんな等しく、サルなのです。
なので、本題に戻りますと、この「方言禁止」なる番組には、差別という要素もあろうが、本質的には、多数派が、ほぼどうでもいい些細な違いをあげつらって、少数派を虐めて楽しむ、という図、
どこの社会でもよく見られる図なのだろうと思います。
しかし、決して褒められた図ではありません。こういうお笑いしかできないお笑い芸人というのに、どれだけ存在意義があるのでしょう。