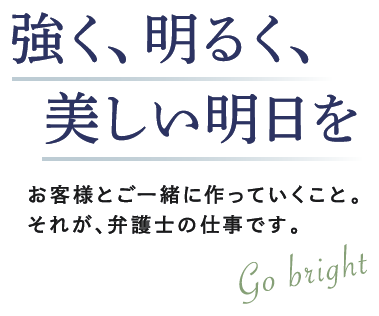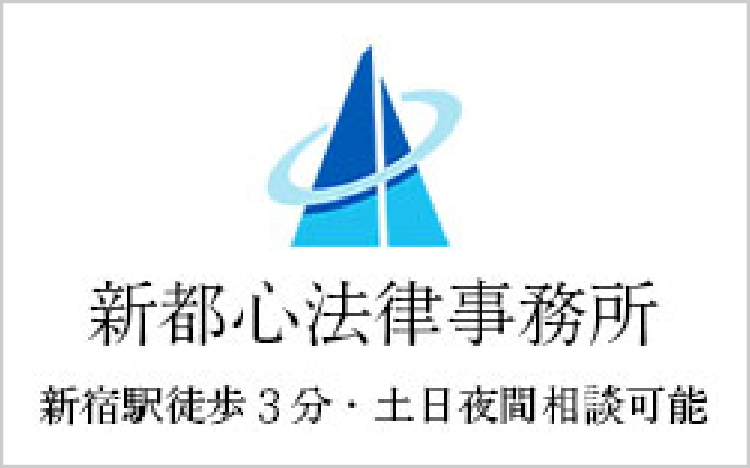2023年12月20日
控訴審から受任する、ということ。
一審で他の先生が担当されて負けた事件を控訴審から受けて逆転して勝つと、
それは、お客さんはめちゃくちゃ喜んでくださいます。
しかし、だからと言って一審で負けた先生がまるでダメな先生だったということになるかというと、そうではありません。
要は、控訴審から担当すると、「一審で、主張Aは通らなかったのだな、この証拠がこう判断されたのだな、だとしたら、控訴審では主張Bに切り替えよう、この証拠はこれで補強しよう」などと、一審での経験を踏まえて、次の方法を考えられるわけで、
その土台となる、「あ、主張Aは、通らないんだ」ってのは、一審を戦っているときには無い情報なわけです。
まあ、一審裁判所が示唆してくれることも多く、それに代理人が気が付くか、というのは一つの問題ではあります。また、そもそも主張Aは、無理筋じゃねえ?という時もあることはあります。
が、ともかく、主張Aはだめだ、という重要な情報が、一審にはなく、控訴審には、ある。
なので、あくまでも一審での敗訴あっての控訴審なので、たとえ控訴審で勝ったとしても、控訴審で逆転したセンセイはエラく、一審でのセンセイがダメである。ということには、ならん。と、私は思います。
クライミングで言うと、要は、一審勝訴ってのはオンサイト(壁を、一発目のトライで登りきること)なのだが、
控訴審はオンサイトではないんです。
控訴審って、このルートは、今の実力(=手持ちの証拠)ではアカンな、とか、このムーブではこの壁は突破できないな、と、判ってからのトライなんです。そりゃ、成功確率も上がるわけですよ。
ただ、これもよくあることなんですが、一回目のトライでダメだった=一審で負けたとき、登っているほうからすると、もう、ほかのルートやほかの方法が思いつきにくくなっています。頭がもう、それ以外のルートを考えられなくなっている。
なので、次のトライに際して、「この主張、あかんのだな、別の主張、何か立たないかな?あ、そうだ、こういう法的構成もあるか!」などと、なかなか思えず、その無理なムーブのままでもう一度壁にトライ=控訴審に突き進み、壁の中でじたばたし、控訴審でもあえなく負けてしまう。ということも、ないわけではありません。
クライミングでこれを続けると腕が疲れ切って登れなくなるんですが、それと同じように、控訴審でも負けると、弁護士はメンタルをやられます。
なので、まあ、一審と二審で弁護士を変える、というのも、一つの選択ではあります。少なくとも控訴審から受任した弁護士は、メンタル、ぴんぴんしてますからね。負けてないから当たり前なんですが。
でもカネはかかるし、必ずしも弁護士を変えたら控訴審で勝てるというわけでもない。当たり前だが、次の弁護士がもっとクライミングが下手だったら、そりゃ、負けるわけですよね。
なので、基本的には、やはり一審で勝つのが一番いいんです、当たり前のことですが。クライミングと一緒で、オンサイトが一番いい。
そのためには、これもクライミングと同じで、一回目のトライをする前に、綿密に壁=資料を読んでルート(法律構成)を探し、最適なルート(最適な法的構成)を見つけ出し、それをまた入念に研究して、どんなムーブ(証拠)でそのルートを突破するか、というのを考えなくてはならないのですが、
が、まあ、現実にはそうもいかんわけです。アルパインクライミングでも、日暮れが迫って十分な時間が取れなかったり、風が寒くて長くそこにいられなったり、そこからみているだけではホールドや落ち口がわからなかったりするのと同じように、
訴訟でも、そんなに時間も金もかけられず、万全の準備ができないままに一審に臨むほかなくなる、ということもあるわけです。
だが、なんにせよ、大事なのはトライで全力を尽くすことで、そして、結果として控訴審で勝ったとしても、決してうぬぼれないことです。控訴審で勝った弁護士が、一審のときの先生をバカにするってのは、下の下です(何かを見ている)。
控訴審で勝ったとしても、それは、一審での敗訴あってこその勝訴なんです。一審を戦い抜いた代理人弁護士に、敬意を。
それは、お客さんはめちゃくちゃ喜んでくださいます。
しかし、だからと言って一審で負けた先生がまるでダメな先生だったということになるかというと、そうではありません。
要は、控訴審から担当すると、「一審で、主張Aは通らなかったのだな、この証拠がこう判断されたのだな、だとしたら、控訴審では主張Bに切り替えよう、この証拠はこれで補強しよう」などと、一審での経験を踏まえて、次の方法を考えられるわけで、
その土台となる、「あ、主張Aは、通らないんだ」ってのは、一審を戦っているときには無い情報なわけです。
まあ、一審裁判所が示唆してくれることも多く、それに代理人が気が付くか、というのは一つの問題ではあります。また、そもそも主張Aは、無理筋じゃねえ?という時もあることはあります。
が、ともかく、主張Aはだめだ、という重要な情報が、一審にはなく、控訴審には、ある。
なので、あくまでも一審での敗訴あっての控訴審なので、たとえ控訴審で勝ったとしても、控訴審で逆転したセンセイはエラく、一審でのセンセイがダメである。ということには、ならん。と、私は思います。
クライミングで言うと、要は、一審勝訴ってのはオンサイト(壁を、一発目のトライで登りきること)なのだが、
控訴審はオンサイトではないんです。
控訴審って、このルートは、今の実力(=手持ちの証拠)ではアカンな、とか、このムーブではこの壁は突破できないな、と、判ってからのトライなんです。そりゃ、成功確率も上がるわけですよ。
ただ、これもよくあることなんですが、一回目のトライでダメだった=一審で負けたとき、登っているほうからすると、もう、ほかのルートやほかの方法が思いつきにくくなっています。頭がもう、それ以外のルートを考えられなくなっている。
なので、次のトライに際して、「この主張、あかんのだな、別の主張、何か立たないかな?あ、そうだ、こういう法的構成もあるか!」などと、なかなか思えず、その無理なムーブのままでもう一度壁にトライ=控訴審に突き進み、壁の中でじたばたし、控訴審でもあえなく負けてしまう。ということも、ないわけではありません。
クライミングでこれを続けると腕が疲れ切って登れなくなるんですが、それと同じように、控訴審でも負けると、弁護士はメンタルをやられます。
なので、まあ、一審と二審で弁護士を変える、というのも、一つの選択ではあります。少なくとも控訴審から受任した弁護士は、メンタル、ぴんぴんしてますからね。負けてないから当たり前なんですが。
でもカネはかかるし、必ずしも弁護士を変えたら控訴審で勝てるというわけでもない。当たり前だが、次の弁護士がもっとクライミングが下手だったら、そりゃ、負けるわけですよね。
なので、基本的には、やはり一審で勝つのが一番いいんです、当たり前のことですが。クライミングと一緒で、オンサイトが一番いい。
そのためには、これもクライミングと同じで、一回目のトライをする前に、綿密に壁=資料を読んでルート(法律構成)を探し、最適なルート(最適な法的構成)を見つけ出し、それをまた入念に研究して、どんなムーブ(証拠)でそのルートを突破するか、というのを考えなくてはならないのですが、
が、まあ、現実にはそうもいかんわけです。アルパインクライミングでも、日暮れが迫って十分な時間が取れなかったり、風が寒くて長くそこにいられなったり、そこからみているだけではホールドや落ち口がわからなかったりするのと同じように、
訴訟でも、そんなに時間も金もかけられず、万全の準備ができないままに一審に臨むほかなくなる、ということもあるわけです。
だが、なんにせよ、大事なのはトライで全力を尽くすことで、そして、結果として控訴審で勝ったとしても、決してうぬぼれないことです。控訴審で勝った弁護士が、一審のときの先生をバカにするってのは、下の下です(何かを見ている)。
控訴審で勝ったとしても、それは、一審での敗訴あってこその勝訴なんです。一審を戦い抜いた代理人弁護士に、敬意を。