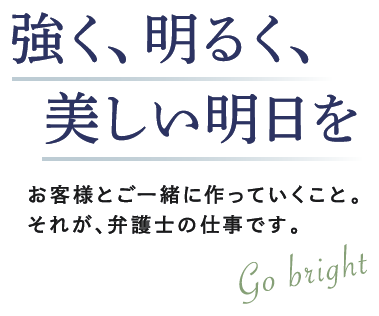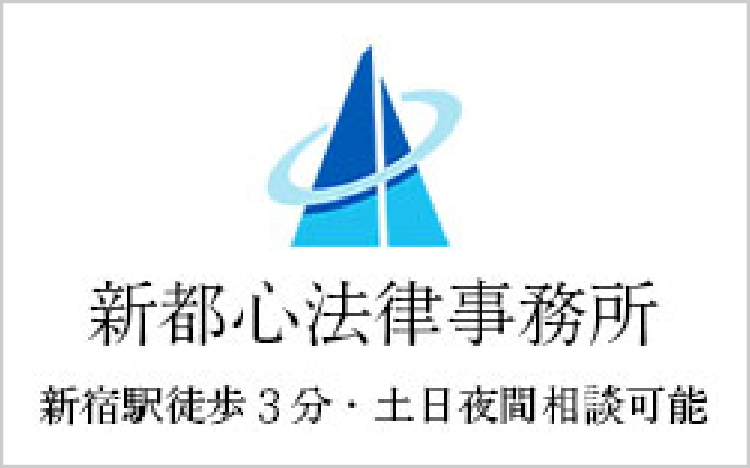2023年04月24日
山林火災からの脱出
今年の沢はじめは、山火事に巻き込まれて脱出するという、やや珍しい経験をしたので、どなたかの参考になることを願って、以下記録です。(長文)
1 火災遭遇とエスケープルート案立案
遭遇は、下山時、メンバーは、夫(L)、野島、新人、ルートは、片品川水系泙川小田倉沢遡行、津室沢下降であった。
津室沢の下降を終え、三重泉沢に入って盛大に休憩してから林道に上がるが、とたんに、焦げ臭く、けぶる。畑焼か、でもここから畑はかなり遠いが。。。。などと話しながら行くと、どんどん白さと臭さが増していく。これは山火事では、と歩を進めると、下(泙川本流付近)からもくもくと煙が上がっているのが見え、しだいに、山肌にも炎が見え始め、これは林道を通過できないのではと案じながらさらに急ぐと、予想通り、林道は一面に燃えており、炎はじわじわと我々の足元に向かってきていた。13時30分。
さて、どうするか。携帯は入らない。
既述のとおり、下方に一か所、激しく煙が出ているところが見える、枝沢と本流とが合流する地点で、火元はそこと推定された。そこから火が山肌を上がり、林道に達し、さらに林道の上の山肌まで燃え広がっている、落石が激しい。
しかし、目を凝らせば、枝沢を超えた向こうの尾根筋からは煙は上がっておらず、炎は、この枝沢を超えた尾根筋まではまだ達していないようであった。つまり、この時点では、林道を含めた山肌が燃えている箇所は、水平距離にして200mほどで、これを何とかして巻ければ、火のない林道に戻れると考えられた。
そこで、泙川本流に下降し、本流を下降してこの火災地帯をやり過ごし、どこかから林道に復帰できないかと考え、本流右岸1187峰の東側からひら川本流に向かって伸びる尾根から本流に下降し、本流を下り、標高960地点から入る枝沢(1187峰と1245峰の間を流れる沢)を遡行して林道に戻る計画を立てた。そこはまだ燃えていないだろうと想像したのだ。ただ、火は刻々と燃え広がっており、急がなければ、林道復帰予定地点にも火が到達することは容易に想像できた。
懸念点は、①泙川本流は水量多く、渡渉を交えるであろう下降に難がないか、②目指す枝沢の遡行があんま、容易じゃなさそう。。。という2点であった。が、それ以外に林道復帰できそうなポイントも地図上には見当たらず、これをトライするよりほかにない。
2 エスケープの実行
ただちに林道を引き返し、緩いところから泙川本流に向け、下降する。懸垂して本流に降り立ち、下降を開始する。巨岩がごろごろするが技術的な困難はなく、案じた渡渉もさほどではなかった。
この途中で火元と思われる地点に遭遇した。1187峰は、南尾根と東尾根をもって泙川本流に達するのだが、ちょうどその二つの尾根間を流れる枝沢の真下から、勢いよく火が上がっており、焚火らしき形跡もあり、そして、河原には失火者と思われる足跡があった。罵りながらそれを通過し、渡渉を繰り返すことしばらく、ようやく目指す復帰用の枝沢を発見する。
うん。これかよ。というご渓相だが、やむを得ない。意を決し、遡行開始。少し上がると、50mほどの滝に遭遇し、ちょっと登れそうにない。滝の右手の泥壁を登れば、その上に岩は見えるが、短く、このルートの方が可能性、ありそう。
この岩さえ超えればこの上に困難はなく、林道に戻れる、まだ炎が来ていなければ、これで帰れる。と思った。そしてこの地点では、きな臭さも、煙もなく、まだ林道に炎は来ていないと思ったのだ。
1ピッチ目、泥壁50mいっぱい、野島リード。支点は二か所灌木でとれるのみ、上部2mはかなり立っており、緊張するが、身中にあるありったけの泥壁愛をかき集め、岩の真下まで登ってピッチを切る。岩は、ちょいハングってるが、ショルダーならなんとかなりそう。フォローを引き上げる。
2ピッチ目、夫リード、空身で、夫が見事にハンマー投げを決めてかけたシュリンゲにA0して突破、その上もちょい難しいが、確実なクライミングで越えてくれた。30mほどで切り、新人を上げ、野島が夫とザックとともに上がる。
3ピッチ目泥壁50mいっぱい、野島リード。この泥壁は極めて野島の好みに合っており、支点はほぼ取れず、墜ちたら死ぬだろうが、墜ちる気はしないし、ともかく急がなければ、炎が来る。50mいっぱい伸ばす。
そこまでくると、あとは緩い。一か所いやらしいトラバースがあり、念のためザイルを出し(4ピッチ目)夫リード、ザイルを固定し、新人を上げ、野島ラスト、二人に先に行ってもらい、私はザイルをしまって、後を追う。標高差は20mほどしかないはずだが、これが本当に長く思われた。
そしてやっと林道が見えた、とたんに、煙が目に入る。
林道が燃えているのだ、ああ、遅かったか、もう炎が来てしまったか、と絶望しかけたが、ともかく全力で走って林道に飛び出す、見ると、炎が来ているのは、まさに私が飛び出したところの1m手前までで、ギリギリ、そこから先は燃えておらず、炎のわきで夫が待ってくれていた。
新人を先に走らせ、二人で足早に奈良の集落に向かって林道を急ぐが、なんと、また手前に炎が見えるではないか。
ここで初めて分かったのだが、当たり前なのだが火は林道伝いにきているとは限らない。今我々が歩いている林道は燃えていないが、炎は、1187峰南尾根の山肌を伝って燃え広がり、その火が下の林道に回ってきて、我々の行く手を燃やしているのであった。
が、幸い、この炎は、まだ林道全面に燃え広がっていなかった。林道の4分の3ほど、落ち葉や枯れ枝が堆積している部分は燃えているが、左端、コンクリートが露出している4分の1は燃えていない、そこを駆け抜けてことなきを得る。
その先は、もう、炎はない。トンネルをくぐり、地形図上981の記載のある個所に至ると、消防がどっさり来ている、誰かが通報したらしい。新人がここで質問攻めにあって困っていたため、私が警察官と消防士に状況を手短に説明すると、彼らは状況を理解して、続々と山に向かってく。17時40分。あとを消防に託し、肩の荷を下ろし、車にたどり着いた。
1330から飲まず食わずの行動、ようやく緊張が解けてのどの渇きを覚え、沢靴のまま車に乗り込んで、コンビニに向かった。
3 教訓
正直、山火事で下山不能になるって想定はしたことがなかったのだが、生じ得るのだ。恐ろしい。
火は、思ったより早く回る。迅速な決断と行動が必須である。
また、今回は火事遭遇時刻1330であり、日暮れまでに時間があったため、本流に降り立って火事を回避して登りなおす、という選択肢を取りえた。これが1時間遅くなっていたら、ヘッデンで泥壁を登ることになっていた。余裕を持った計画大事。
そして、パートナー大事。こういう時に、短時間の協議で意思疎通でき、相手の判断とクライミング能力を信頼して行動できるパートナーというのは全くありがたいものである。
最後に、泥壁大事。こういう時、泥壁が登れなかったら即アウトである。泥壁を愛せよ。我が国のヤマにおいては、泥壁登りは必須なのである。

1 火災遭遇とエスケープルート案立案
遭遇は、下山時、メンバーは、夫(L)、野島、新人、ルートは、片品川水系泙川小田倉沢遡行、津室沢下降であった。
津室沢の下降を終え、三重泉沢に入って盛大に休憩してから林道に上がるが、とたんに、焦げ臭く、けぶる。畑焼か、でもここから畑はかなり遠いが。。。。などと話しながら行くと、どんどん白さと臭さが増していく。これは山火事では、と歩を進めると、下(泙川本流付近)からもくもくと煙が上がっているのが見え、しだいに、山肌にも炎が見え始め、これは林道を通過できないのではと案じながらさらに急ぐと、予想通り、林道は一面に燃えており、炎はじわじわと我々の足元に向かってきていた。13時30分。
さて、どうするか。携帯は入らない。
既述のとおり、下方に一か所、激しく煙が出ているところが見える、枝沢と本流とが合流する地点で、火元はそこと推定された。そこから火が山肌を上がり、林道に達し、さらに林道の上の山肌まで燃え広がっている、落石が激しい。
しかし、目を凝らせば、枝沢を超えた向こうの尾根筋からは煙は上がっておらず、炎は、この枝沢を超えた尾根筋まではまだ達していないようであった。つまり、この時点では、林道を含めた山肌が燃えている箇所は、水平距離にして200mほどで、これを何とかして巻ければ、火のない林道に戻れると考えられた。
そこで、泙川本流に下降し、本流を下降してこの火災地帯をやり過ごし、どこかから林道に復帰できないかと考え、本流右岸1187峰の東側からひら川本流に向かって伸びる尾根から本流に下降し、本流を下り、標高960地点から入る枝沢(1187峰と1245峰の間を流れる沢)を遡行して林道に戻る計画を立てた。そこはまだ燃えていないだろうと想像したのだ。ただ、火は刻々と燃え広がっており、急がなければ、林道復帰予定地点にも火が到達することは容易に想像できた。
懸念点は、①泙川本流は水量多く、渡渉を交えるであろう下降に難がないか、②目指す枝沢の遡行があんま、容易じゃなさそう。。。という2点であった。が、それ以外に林道復帰できそうなポイントも地図上には見当たらず、これをトライするよりほかにない。
2 エスケープの実行
ただちに林道を引き返し、緩いところから泙川本流に向け、下降する。懸垂して本流に降り立ち、下降を開始する。巨岩がごろごろするが技術的な困難はなく、案じた渡渉もさほどではなかった。
この途中で火元と思われる地点に遭遇した。1187峰は、南尾根と東尾根をもって泙川本流に達するのだが、ちょうどその二つの尾根間を流れる枝沢の真下から、勢いよく火が上がっており、焚火らしき形跡もあり、そして、河原には失火者と思われる足跡があった。罵りながらそれを通過し、渡渉を繰り返すことしばらく、ようやく目指す復帰用の枝沢を発見する。
うん。これかよ。というご渓相だが、やむを得ない。意を決し、遡行開始。少し上がると、50mほどの滝に遭遇し、ちょっと登れそうにない。滝の右手の泥壁を登れば、その上に岩は見えるが、短く、このルートの方が可能性、ありそう。
この岩さえ超えればこの上に困難はなく、林道に戻れる、まだ炎が来ていなければ、これで帰れる。と思った。そしてこの地点では、きな臭さも、煙もなく、まだ林道に炎は来ていないと思ったのだ。
1ピッチ目、泥壁50mいっぱい、野島リード。支点は二か所灌木でとれるのみ、上部2mはかなり立っており、緊張するが、身中にあるありったけの泥壁愛をかき集め、岩の真下まで登ってピッチを切る。岩は、ちょいハングってるが、ショルダーならなんとかなりそう。フォローを引き上げる。
2ピッチ目、夫リード、空身で、夫が見事にハンマー投げを決めてかけたシュリンゲにA0して突破、その上もちょい難しいが、確実なクライミングで越えてくれた。30mほどで切り、新人を上げ、野島が夫とザックとともに上がる。
3ピッチ目泥壁50mいっぱい、野島リード。この泥壁は極めて野島の好みに合っており、支点はほぼ取れず、墜ちたら死ぬだろうが、墜ちる気はしないし、ともかく急がなければ、炎が来る。50mいっぱい伸ばす。
そこまでくると、あとは緩い。一か所いやらしいトラバースがあり、念のためザイルを出し(4ピッチ目)夫リード、ザイルを固定し、新人を上げ、野島ラスト、二人に先に行ってもらい、私はザイルをしまって、後を追う。標高差は20mほどしかないはずだが、これが本当に長く思われた。
そしてやっと林道が見えた、とたんに、煙が目に入る。
林道が燃えているのだ、ああ、遅かったか、もう炎が来てしまったか、と絶望しかけたが、ともかく全力で走って林道に飛び出す、見ると、炎が来ているのは、まさに私が飛び出したところの1m手前までで、ギリギリ、そこから先は燃えておらず、炎のわきで夫が待ってくれていた。
新人を先に走らせ、二人で足早に奈良の集落に向かって林道を急ぐが、なんと、また手前に炎が見えるではないか。
ここで初めて分かったのだが、当たり前なのだが火は林道伝いにきているとは限らない。今我々が歩いている林道は燃えていないが、炎は、1187峰南尾根の山肌を伝って燃え広がり、その火が下の林道に回ってきて、我々の行く手を燃やしているのであった。
が、幸い、この炎は、まだ林道全面に燃え広がっていなかった。林道の4分の3ほど、落ち葉や枯れ枝が堆積している部分は燃えているが、左端、コンクリートが露出している4分の1は燃えていない、そこを駆け抜けてことなきを得る。
その先は、もう、炎はない。トンネルをくぐり、地形図上981の記載のある個所に至ると、消防がどっさり来ている、誰かが通報したらしい。新人がここで質問攻めにあって困っていたため、私が警察官と消防士に状況を手短に説明すると、彼らは状況を理解して、続々と山に向かってく。17時40分。あとを消防に託し、肩の荷を下ろし、車にたどり着いた。
1330から飲まず食わずの行動、ようやく緊張が解けてのどの渇きを覚え、沢靴のまま車に乗り込んで、コンビニに向かった。
3 教訓
正直、山火事で下山不能になるって想定はしたことがなかったのだが、生じ得るのだ。恐ろしい。
火は、思ったより早く回る。迅速な決断と行動が必須である。
また、今回は火事遭遇時刻1330であり、日暮れまでに時間があったため、本流に降り立って火事を回避して登りなおす、という選択肢を取りえた。これが1時間遅くなっていたら、ヘッデンで泥壁を登ることになっていた。余裕を持った計画大事。
そして、パートナー大事。こういう時に、短時間の協議で意思疎通でき、相手の判断とクライミング能力を信頼して行動できるパートナーというのは全くありがたいものである。
最後に、泥壁大事。こういう時、泥壁が登れなかったら即アウトである。泥壁を愛せよ。我が国のヤマにおいては、泥壁登りは必須なのである。