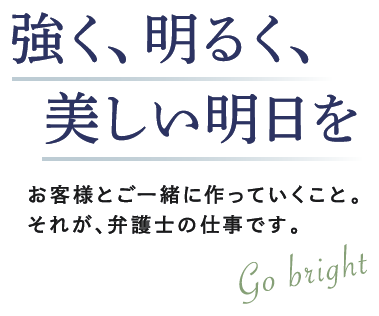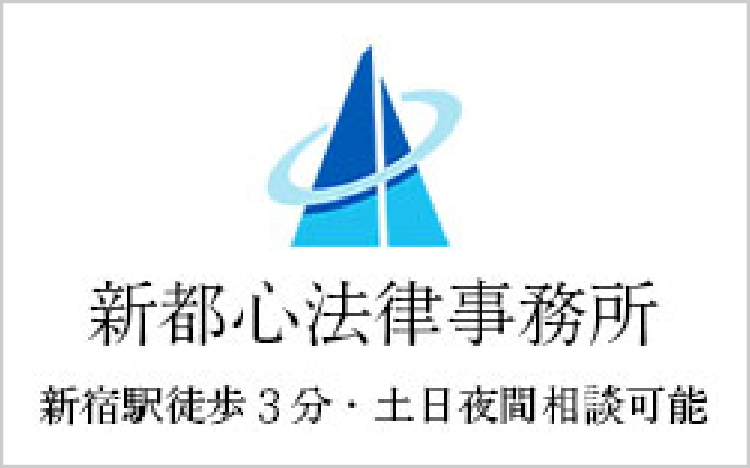2021年12月24日
子が拒んでいるにもかかわらず母と子の面会交流を認容した家裁の保全処分について
おそらく12~13歳くらいで、今、父親に監護されているお子さんが、母と会いたくないと言っている案件において、母と会わせよ、という保全命令が出て、父が抗告したが棄却された、という事案です。仙台家裁が原審、抗告審が仙台高裁ですね。
これはなかなか味わい深い保全命令です。
前提として、母が末期がんであること、どうやら父が何らかの宗教に凝っていて、お子さんもその影響を受けているらしい、という事実関係が見て取れます。その上で裁判所は、お子さんが母親に会いたくないと言っているのは、今お子さんの身近にいる大人たち(父や宗教関係者含む)の影響である、いまお子さんが自ら母に会う機会を拒絶したとなれば、お子さんの将来に取り返しのつかない悔いを残すことになりかねないとして、「母親の病状に鑑みれば、お子さんの福祉のため、早期に面会交流を実施させるべき」という判断を示しました。
へええええー。というい感じです。これ、父母が逆だったとしも、裁判所、同じように言ってくれるのでしょうかね。父と子の面会交流にはだいぶ、やる気ない感じですけどね、東京家裁は。
私は面会交流について、延々と調停でやることにあまり意味があるとは思っていません。というか面会交流は、本来法律家が扱える域を超えてると感じています。我々条文屋さんであり喧嘩屋さんであって、お子さんの心理とかの専門家じゃないんで。
ともかく面会交流の調停はもめて長引くのですが、確実に増えてきています。なので、これが家裁をめっちゃ圧迫していて、家裁を萎えさせているというか、もう家裁が疲れ果ててやる気を失っているように感じるんですよね。違ったらごめんなさい、家裁のひと。
わたしゃ、面会交流は、家裁からちょいと独立させて別の機関を作るべきだと思うんですよね。ほら、東京地裁から執行センターがちょいと独立(独立じゃないけど、まあ、半分独立したようなもんです)したように。もっとがっちり専門家を入れて。調停委員より必要なのは調査官ですしね。
父も母も本来的には子の幸せを願っているんです。調査官も調停委員も、我々も。それでもなぜかうまくいかない。家族というのはなかなか、難しいもんです。
これはなかなか味わい深い保全命令です。
前提として、母が末期がんであること、どうやら父が何らかの宗教に凝っていて、お子さんもその影響を受けているらしい、という事実関係が見て取れます。その上で裁判所は、お子さんが母親に会いたくないと言っているのは、今お子さんの身近にいる大人たち(父や宗教関係者含む)の影響である、いまお子さんが自ら母に会う機会を拒絶したとなれば、お子さんの将来に取り返しのつかない悔いを残すことになりかねないとして、「母親の病状に鑑みれば、お子さんの福祉のため、早期に面会交流を実施させるべき」という判断を示しました。
へええええー。というい感じです。これ、父母が逆だったとしも、裁判所、同じように言ってくれるのでしょうかね。父と子の面会交流にはだいぶ、やる気ない感じですけどね、東京家裁は。
私は面会交流について、延々と調停でやることにあまり意味があるとは思っていません。というか面会交流は、本来法律家が扱える域を超えてると感じています。我々条文屋さんであり喧嘩屋さんであって、お子さんの心理とかの専門家じゃないんで。
ともかく面会交流の調停はもめて長引くのですが、確実に増えてきています。なので、これが家裁をめっちゃ圧迫していて、家裁を萎えさせているというか、もう家裁が疲れ果ててやる気を失っているように感じるんですよね。違ったらごめんなさい、家裁のひと。
わたしゃ、面会交流は、家裁からちょいと独立させて別の機関を作るべきだと思うんですよね。ほら、東京地裁から執行センターがちょいと独立(独立じゃないけど、まあ、半分独立したようなもんです)したように。もっとがっちり専門家を入れて。調停委員より必要なのは調査官ですしね。
父も母も本来的には子の幸せを願っているんです。調査官も調停委員も、我々も。それでもなぜかうまくいかない。家族というのはなかなか、難しいもんです。